AMEDシンポジウム2019開催レポート AMEDシンポジウム2019開催レポート(2日目):ワークショップ
 ワークショップ①ライフステージとつながるデータ
ワークショップ①ライフステージとつながるデータ

- 登壇者
- 小林 徹氏(国立成育医療研究センター)
- 栗山 進一氏(東北大学)
- 柳田 紀之氏(相模原病院)
- 尾崎 紀夫氏(名古屋大学)
- 矢作 尚久氏(慶應義塾大学)
ライフステージとゲノム、環境要因、生活習慣、健康状態等のライフコースを俯瞰した様々なデータがつながることで、新たな予防等に関する研究開発の可能性があります。本WSでは5名の先生方に、各々の専門領域を中心に、テーマに沿ってご討議いただきました。
周産期・胎児期から乳幼児期の環境と母児の予後との関連研究と臨床研究推進、アレルギーマーチや思春期女性の極端な痩せを背景とした身体・こころの課題へのアプローチ、およびそれらを支援するライフコースデータ整備について、同意制御や情報流通基盤のグランドデザインが紹介され、基盤技術の実装による予防やヘルスケアの実現について議論されました。
 ②医療研究開発における患者・市民参画(PPI)
②医療研究開発における患者・市民参画(PPI)

- 登壇者
- 武藤 香織氏(東京大学)
- 天野 慎介氏(全国がん患者団体連合会)
- 八代 嘉美氏(日本再生医療学会)
- 西川 智章氏 (日本製薬工業協会)
患者と研究者の協働による成果創出に向けて、医療研究開発における患者・市民参画(Patient and Public Involvement, PPI)の取組や重要性、今後の展望・課題について、医療研究開発を担う様々なステークホルダーの先生方にご登壇いただき、フロアとの活発な意見交換も行うことで、議論を深めることができました。
 ③レギュラトリーサイエンス―医薬品の効率的な開発と安全な使用のために―
③レギュラトリーサイエンス―医薬品の効率的な開発と安全な使用のために―
- 登壇者
- 奥田 晴宏氏(国立医薬品食品衛生研究所)
- 斎藤 嘉朗氏(国立医薬品食品衛生研究所)
- 林 邦彦氏(群馬大学)
レギュラトリーサイエンスの両輪であるウェット研究とドライ研究として、それぞれ、医薬品による重篤副作用のバイオマーカー開発とクリニカル・イノベーション・ネットワーク横串班の成果を紹介いたしました。

奥田 晴宏氏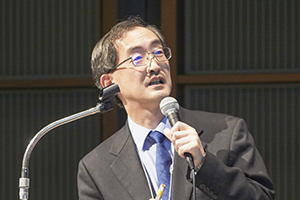
斎藤 嘉朗氏
林 邦彦氏
 ④お悩み解決!認知症コホート・レジストリ研究の”あるある”
④お悩み解決!認知症コホート・レジストリ研究の”あるある”
- 登壇者
- 池内 健氏(新潟大学)
- 岩坪 威氏(東京大学)
- 二宮 利治氏(九州大学)
- 數井 裕光氏(高知大学)
- 花川 隆氏(京都大学)
- 鈴木 啓介氏(国立長寿医療研究センター)
認知症の研究発展には、認知機能低下が無い方の研究協力が必要ですが、協力者が集まりにくいのが悩みです。当日は、認知症研究の第一線の研究者から研究の話をうかがい、理解を深めていただきました。
コホート/レジストリ研究の重要性を知っていただき、さらには認知症のコホート/レジストリ研究の推進につながる意見交換ができるよい機会となりました。研究者の方々からは各研究にて様々ご苦労されている点も忌憚なくお話しいただき、また会場からのご質問にお答えいただきながら、多くの方々の真摯なご尽力で支えられているコホート/レジストリ研究について、ポジティブな討論となりました。

 ⑤ゲノム医療研究におけるデータシェアリング
⑤ゲノム医療研究におけるデータシェアリング
- 登壇者
- 春日 雅人PD(AMED疾病克服に向けたゲノム医療実現プロジェクト)
- 中川 英刀 PO 、小崎 健次郎 PO (AMEDゲノム医療実現推進プラットフォーム事業)
- 土原 一哉氏(国立がん研究センター)
- 古澤 嘉彦氏(武田薬品工業)
- 長神 風二氏(東北大学)
- 松田 浩一氏(東京大学)
- 後藤 雄一氏(国立精神・神経医療研究センター)
- 荻島 創一氏(東北大学)
医療に貢献する先駆的データシェアリングと、開かれたバイオバンクにおける未来志向のデータシェアリングについて、GEM Japan、IRUD Exchange、SCRUM Japan、難病プラットフォーム、3大バイオバンク※とバイオバンク連携等に関する取組事例をご報告いただきました。
※3大バイオバンク:東北メディカル・メガバンク、バイオバンク・ジャパン、ナショナルセンターバイオバンクネットワーク(NCBN)

春日 雅人PD
中川 英刀PO
小崎 健次郎PO

土原 一哉氏
古澤 嘉彦氏
長神 風二氏

松田 浩一氏
後藤 雄一氏
荻島 創一氏
 ⑥新進気鋭の若手・女性研究者が見据える未来医療―AMED先端研究の今―
⑥新進気鋭の若手・女性研究者が見据える未来医療―AMED先端研究の今―
- 登壇者
- 後藤 義幸氏(千葉大学)
- 岡田 随象氏(大阪大学)
- 西村 栄美氏(東京医科歯科大学)
- 谷内江 望氏(東京大学)
- 渡邉 力也氏(理化学研究所)
「革新的先端研究開発支援事業」および「老化メカニズムの解明・制御プロジェクト」に参画する5名の若手・女性研究者が、最新の研究成果をご紹介するとともに、生命系基礎研究が創る未来医療について議論頂きました。
後藤先生からは、糖鎖α1,2-フコースを介した腸管における細菌と宿主の相互作用の解明と、今後の応用展開をお話いただきました。岡田先生は、遺伝統計学の立場から、メタゲノムワイド関連解析を用いた疾病と微生物叢の関係を明らかにする取り組みを紹介しました。
西村先生は、表皮の幹細胞の研究を通じて、若さの維持と加齢変化に幹細胞競合が関わるなど最新の研究成果を交え、皮膚老化のメカニズムについて紹介しました。
谷内江先生からは、細胞分裂の系譜を記録するDNAメモリーシステムの開発と細胞系譜再構築のプラットフォーム作りについてご紹介いただきました。
渡邉先生は、半導体製造技術を応用して人工生体膜チップを作成し、医薬品の主要な標的である膜タンパク質の機能を1分子スケールで効率的に測定する技術を紹介しました。

後藤 義幸氏
岡田 随象氏
西村 栄美氏

谷内江 望氏
渡邉 力也氏
最終更新日 令和2年10月23日


