AMEDシンポジウム2017開催レポート:AMEDの現在と未来(1)
 AMEDシンポジウム1日目(5月29日)AMEDの現在と未来―グローバルなデータシェアリングによる研究開発の推進―
AMEDシンポジウム1日目(5月29日)AMEDの現在と未来―グローバルなデータシェアリングによる研究開発の推進―
末松 誠(AMED理事長)
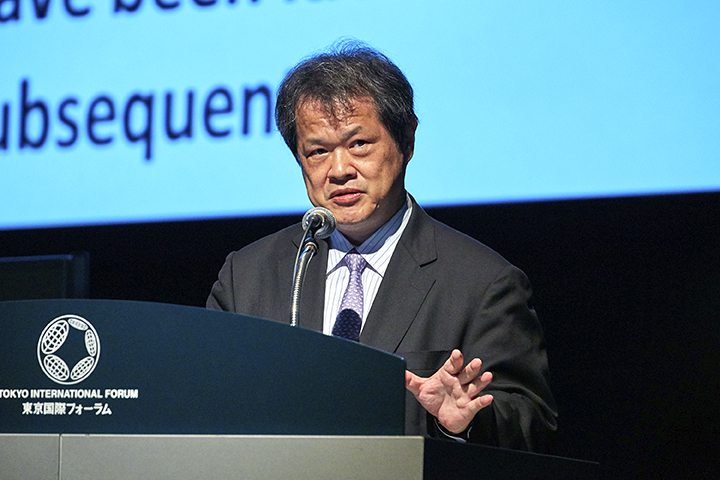
日本医療研究開発機構(以下、AMED)が発足してから2年。医療研究開発の成果を病気で苦しんでいる方々に少しでも早く届けることを使命として、研究開発事業の円滑な運営はもちろん、研究費を機能的に運用するためのルール作りや、国際連携の強化、若手研究者の育成などに積極的に取り組んできました。未診断疾患イニシアチブ(IRUD)では、これまで病名の診断がつかず治療方法も分からずに困っていた患者さんに対して、遺伝子解析を行い総合的な診断を提供するための体制を構築し、着実に成果が上がりつつあります。理事長としてこの2年、強力なリーダーシップでAMEDを牽引してきた末松理事長が、AMEDのこの2年間の取り組みとこれからについて講演しました。
日本の医療研究開発の充実と加速をめざして
AMEDは、医療分野の研究開発の成果を一刻も早く実用化し、患者さんやご家族のもとにお届けすることを目指して設立されました。医療の研究開発は、スポーツに例えると、“マラソン”ではなく、異なる研究分野の専門家がたすきをつないで、ゴールを目指す“駅伝”です。ところが、AMED設立前は文部科学省、厚生労働省、経済産業省で別々に研究開発が行われており、基礎研究、応用研究、臨床研究、実用化という開発のフェーズがスムーズにつながっていませんでした。そこで3省の医療研究に関する事業をAMEDに集約し、予算を一元化し、重点的・戦略的に配分することで、基礎から実用化まで切れ目なく研究を進めることを目指しています。現在の予算は、年間約1500億円です。
研究費を効果的・効率的に使っていただくために機能的運用を実現
研究開発のスピードを加速するためには、研究費を効果的・効率的に使っていただく環境の整備が必要です。ところが、これまでは文部科学省、厚生労働省、経済産業省で別々のルールが適用されており、また研究者にとって利用しづらい面が多々ありました。
そこで、まず研究費を機能的に運用するために、研究機関の事務作業の軽減を考慮しながらルールの統一化と柔軟化を行いました。
この見直しは非常にうまくいきました。まだルールが変わったことをよくご存知ない研究機関の方々もいらっしゃいますので積極的に周知していきます。また、今後は間接経費の弾力的な運用や透明化にも取り組んでいこうと思っています。
最終更新日 平成29年10月16日


