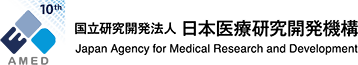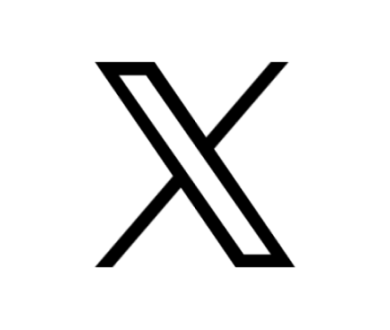アーカイブ インタビューNo.3「新たなアクションを起こすために」

理化学研究所 統合生命医科学研究センター
ゲノムシーケンス解析研究チーム チームリーダー
外科医としてがん治療の現場に立たれた後、米国で遺伝性腫瘍の研究・ゲノム医療の経験を積み、帰国後はがんゲノム研究者の道を選ばれた中川 英刀先生。臨床医としての経験と視点を持ち続ける研究者・プログラムオフィサーから見た、ゲノム研究・医療とバンクの関係についてお話を伺いました。
臨床から研究へ、ゲノムとともに
― 臨床から研究に専念なさった時期は、ヒトゲノムの解読(ドラフト)終了と重なりますが、ゲノムやゲノム研究に対してどのような印象をお持ちでしたか?
ちょうどアメリカで遺伝性腫瘍※1のゲノム研究をしていたころで、発表されたドラフトの情報を使っていました。BRCA※2やリンチ症候群※3の原因遺伝子がわかってきて、臨床現場に解析結果をフィードバックする、いわゆるゲノム医療が行われていた頃です。すでに明らかになっている変異は通常のシークエンシングで特定し、その方法では原因が特定できなかったサンプルについて、当時最先端のゲノム解析技術を使って変異を見つけるという研究をしていました。新たな変異が見つかった場合は、その結果を遺伝子カウンセラーと一緒に患者にフィードバックしていたので、ゲノム医療に、現場というよりは周辺で関わっていました。だからゲノム研究の成果を医療利用することに違和感はなかったですね。
ゲノムというものに対しては、無限ではない、というイメージを強く持っています。ICGC(International Cancer Genome Consortium、国際がんゲノムコンソーシアム) ※4では、2008年から、がんの全ゲノムシークエンスを行っています。ゲノム全体、つまり30億塩基を、正確性のために30回読めば約100G(ギガ)塩基数のデータになります。G、つまり無限ではないのです。T(テラ)でもP(ペタ)でも無限でない。10年前はGとはすごい大きさだと思っていましたが、今やUSBメモリレベルです。バイオインフォマティシャンが増え、コンピューターの精度も容量もどんどん上がってきました。2008年当時の次世代シークエンサーは一度に3Gしか読めないうえ、正常組織とがん組織とを比較するからデータ量は倍。気が遠くなるような作業でしたが、3ヶ月毎に技術は向上し、約10年を経た今は一度に1000G以上読んでいます。改めて、ヒトゲノムが無限ではないことと、技術の進歩を実感しています。
アクションが起こせるということ

― 本コーナー最初のインタビュイーである高坂先生が、ゲノム医療で最も成功しているのはがんだろうと語られていました。分子標的薬が開発されていることも成果の1つといえるだろうと。がんが他の疾病をリードできている要因は何だとお考えですか?
がんは治療方法がある・早期発見での治癒が期待できる、というのが要因ではないでしょうか。何らかの医療的アクションが取れるというのが、医療が発展するという点では大切です。診断するだけでは患者さんにとってメリットが多くないですから。だから、がんのゲノム医療のエンドポイントは、現時点では治療法がないがんの患者に対して、新たな治療法が見つかる、発症前に何らかの早期発見、予防措置が取れるなど、ゲノム診断後にアクションできるようになることではないかと思っています。 コンパニオン診断薬※5もセットになって、ゲノム情報に基づいたさまざまな治療が、がんの領域では広がっていると言えるでしょう。例えばドライバー遺伝子変異※6が見つかり、それを標的として薬を作る、あるいはコンパニオン診断で薬の使い分けするというコンセプトができてきたのはよいことです。 ただし、それでがんのすべてを説明はできるわけではなく、効かない人のほうがむしろ多いんです。がん免疫治療も効くのは10~15%程度。AMED「がんゲノム医療推進プロジェクト」や世界のがん臨床シークエンスでは、がん関連遺伝子パネル※7を利用した臨床試験が進められていますが、最終的に薬にありつけるのは5~15%。10%に向けて希望が見えてきたという状況です。
― がんはゲノムレベルでの多様性が高いということがネックなのでしょうか?
一人ひとりのがんの変異データは、究極全部違います。そして薬によるアクションが起こせるケースも、今はまだ少ないですね。例えばp53遺伝子が原因のがんは多くて、大腸がんであれば50%くらい。しかし、それに対する薬はまだない。薬が少ないだけでなく、アクセシビリティもよくない。研究も、創薬開発も、まだまだ進む余地があるでしょう。
― がんのゲノム医療が、いつまでにどこまで進むかといった見通しはお持ちですか?
わからないですね。製薬会社が頑張るしかないと思う(笑)。でも、色々な新しいツールができています。がんの本質的要素であるゲノムの不安定性※8を標的とした薬や、それと関連するがんの免疫原性を標的とした薬も出てきました。BRCA1、BRCA2などのPARP阻害剤※9は、まさにゲノム不安定性を標的としています。今後もさまざまなコンセプトの創薬が開発されると期待しています。
さらに先に進むためのバンクとは
― がんの研究・創薬にとってもバイオバンクの存在は重要だと思いますが、特にどういった要素・特性が必要だと思いますか?
ICGCではがんゲノムをどんどんシークエンスして、データベース化し、共有してきました。2018年で終了しますが、2万例くらいあります。アカデミアだけでなく製薬企業もデータをシェアして、研究も創薬も進めてもらいたいというコンセプトです。 このICGCでの経験に照らしてバンクの規模について考えると、数があるということは希少がんの研究にとって意義があります。通常の肺がんであれば、大きな病院なら一院だけで年間数百例集められるが、希少がんや小児がんの例数は少ないですから。ゲノム情報も、もちろん少ない。だから希少がんについては、とにかく全国規模で数が集まることが重要だと思います。 しかし通常のがんは、数百例数を集めるだけでは価値が低い。数万、数十万例集めて、例えば日本の乳がんと米国の乳がんとで違いがあるかどうかを検証するというような、日本特有の情報を集めることは大切だと思っています。もっと大事なことは、ゲノムデータに、プラス臨床情報として、「こういう薬を投与した際にこういうレスポンスがあった、延命した」といった綿密な臨床情報があると、バンクとしてより価値が高くなると思うのです。
― ゲノム医療への期待や課題だとお考えになっていることをお聞かせください。
日本では、ゲノム医療やゲノム解析を担える人材や施設、企業が、海外と比べると極端に少ないですね。カウンセラー、解析者、ゲノム解析プラットフォームの運営人材、あらゆるところで足りていない。研究レベルでもゲノム解析に関わる研究者は、海外に比べると圧倒的に少ないし、予算もない状況です。 ゲノム医療が根付いていない要因の1つは、日本の医療制度にフィットしていないからではないでしょうか。米国の仕組みすべてが良いとは思わないですし、日本の皆保険制度はとても良い制度です。だが現状、ゲノム医療やゲノム解析は健康保険の対象にはなっておらず、自費でやろうとする人も少ないです。保険収載されれば、そこに人材提供する意義が見い出されて育成につながり、企業も病院も参画できるようになります。ただし、皆保険制度が費用の問題を抱えている中、すべて保険適用することは難しいでしょう。米国には皆保険制度はない代わりに、多様な民間の保険サービスが用意されています。日本の医療制度に合ったゲノム医療ができて欲しいと思っています。 そして、今後は、"ゲノムからがんのリスクを見る"という臨床に前向きに向かっていくべきではないでしょうか。進行がんの治癒は依然難しいので、早期発見につながる病気のリスクをゲノム情報できっちり評価して、リスクが高い人に対して可能な予防や早期発見策を講じていくというスタンスは重要でしょう。
「リスクがわかる」ことの意義と課題

― 発症前にリスクがわかることは、社会的な問題をはらんでいるのではないでしょうか。
もちろん。日本人には「実はこういうリスクがある」というようなことは知りたくないという精神性があるかもしれません。知りたいけど怖い。言霊信仰のように、口にしたら現実化してしまうかもしれないから、不吉なことは話さない・知りたくない、と。また、遺伝ということにいいイメージをもっていないように感じます。米国で研究していた時に、通常の手法では見つからなかったリンチ症候群の患者の変異が見つかり、告知した思い出があります。その時、がんを発症していない家族も含めて「姪っ子に見つかったって聞いたから、リスクがあるなら自分も調べてくれ」と総勢30名くらいが集まり、さながら親族会のようになったのです。日本ではそういう発想にならないでしょうね。 加えて日本では遺伝子情報差別禁止法(GINA)※10のような法律が未整備です。アメリカの医療保険は個人の責任で加入しますが、そこで遺伝情報が加入拒否につながらないように、"最後の砦"が整備されています。

― カウンセリングの重要性に対する理解や、法的整備はまだ足りないということでしょうか?
ゲノム医療は、問題になるかもしれない情報を見つけ、それを解釈し、患者・家族に説明してお返しする。日本でそれができる人材は少ないです。一義的には主治医が担うのが一番ですが、主治医であっても疾患横断的にすべての知識があるわけではなく、特に希少疾患については難しいでしょう。 シークエンスして疑いが出た時、それがBRCA1、2の遺伝子でのバリアントだったとして、それが病原性のものであるのか、それとも量的なことで問題が起こるのか、発がんと関係が必ずしもはっきりしないものが多いのです。人種差もあると考えられています。だからVUS(Valiant of Uncertain Significance)※11を解釈するための日本人のデータベースの整備が必要です。バリアントの意義を解明するには、同じバリアント持った人同士の比較や人種比較が大切ですが、データベースがないと解釈できないのです。だから日本人の集団としてのデータは大切だし、バリアント・データベースを整備したいと考えています。
AMEDと研究を支えるみなさんへのメッセージ
― AMEDの役割について、先生のお考えをお聞かせください。
AMED設立以前のことはあまり知りませんが、私は理化学研究所に所属しているので、厚生労働省系でなく文部科学省系の研究をしてきました。そうした中、AMED設立によって末松 誠理事長がおっしゃっていた「横串・縦串」でいうところのゲノム解析・医療という「横串」ができた(府省が「縦串」)と感じました。縦割り制度だと、がん・難病・感染症といった疾病毎に分類されるが、ゲノム解析・医療が横串として全体をつなげます。ゲノムは技術であり、疾患横断的な概念です。疾患・省庁横断的な考え方や研究の進め方ができるようになったことは、AMEDができてよかった点と言えるでしょう。残念なのは、AMEDがまだ独自の財源を持っていないところです。関連省庁からの予算取りまとめだけでなく、ぜひ独自の予算を持って欲しいと思っています。
(取材日:2017年9月12日)
用語解説
- *1)遺伝性腫瘍
- 親から子に伝わった、ひとつの遺伝子での病的な変異により発症するがんのこと。父親または母親由来のがん抑制遺伝子に、生まれつきの変異があることが原因であることが多い。
- *2)BRCA
- 遺伝性乳がんの80%は、BRCA1(50%)とBRCA2(30%)の変異によるものと考えられている。生涯乳がんが発症するのはBRCA1で65~80%、BRCA2で45~85%(日本における女性の乳がん発症生涯リスクは8.2%)。発症年齢が低い傾向や卵巣がんの発症率も高いほか、男性における乳がん(BRCA2で6%)や前立腺がんの発症リスク上昇にも関わっている。
- *3)リンチ症候群
- 遺伝性大腸がんのひとつで、大腸がんの2~3%を占めると考えられている。一般より若い年齢で発症しやすいほか、子宮内膜、小腸、腎盂・尿管などのがんも発症しやすく、わが国では胃がんの罹患頻度も高いことが報告されている。
- *4)ICGC(International Cancer Genome Consortium、国際がんゲノムコンソーシアム)
- がん遺伝子の国際的共同研究プロジェクトで、2008年発足し、2016年8月時点で、17か国が参画。日本からは、国立がん研究センターや理化学研究所などが参画。89種類のがんについて各500以上の症例を集めて高精度に解析する作業を分担して進めている。 (小学館 日本大百科全書より引用。
- *5)コンパニオン診断薬
- 特定の医薬品の有効性や安全性を一層高めるために、その使用対象患者に該当するかどうかなどをあらかじめ検査する目的で使用される診断薬。 ((独)医薬品医療機器総合機構Pmdaより引用)
- *6)ドライバー遺伝子変異
- がん細胞の増殖や生存に有利に作用する遺伝子変異。細胞生物学的な機能が明らかになっていない変異も含まれる。 (羊土社 実験医学onlineより抜粋)
- *7)がん関連遺伝子パネル
- 診療上重要な複数の遺伝子の変異、増幅や融合を同時に解析することができるアッセイキット。
- *8)ゲノムの不安定性
- がん細胞では染色体の均等に分配されず(染色体不安定性)、それによる遺伝子発現の変化ががんの薬剤抵抗性や他臓器への転移につながっている。正常細胞内で染色体の不安定性を是正するタンパク質複合体が、がん細胞では不足していることが確認されており、この不安定性を正常化するのではなく、細胞が生存できないほど亢進させる抗腫瘍効果を期待する考え方がある。
- *9)PARP阻害剤
- DNA損傷に応答する機構に異常をきたしたがん細胞に、細胞死を誘導するもの。損傷したDNAを修復する酵素の1つPARPを、やはりDNA修復に関与するBRCA1/BRCA2に変異があるがん細胞で抑制すると、DNA修復ができずにゲノム不安定性が著しく高まり、がん細胞が死滅する。
- *10)遺伝子情報差別禁止法(GINA)
- 2008年5月21日にアメリカ大統領署名により成立した連邦法で、医療保険会社や雇用主が個人の遺伝情報に基づいて米国民を差別するもの。
- *11)VUS(Valiant of Uncertain Significance)
- 「意義不明の変異」と呼ばれるもの。1%以上の頻度でみられる遺伝子多型の大部分に病的意義はないが、比較的低リスクの遺伝病の原因遺伝子変異となる場合がある。一方、既知の遺伝性疾患の原因遺伝子に1%以下の頻度で認められる低頻度の変異の多くは検査会社の報告書でVUSとして取り扱われる場合が多い。 (メディカルビュー社「M-Review」より引用)
推薦論文
- タイトル
- Distribution and clinical impact of functional variants in 50,726 whole-exome sequences from the DiscovEHR Study
- 著者名
- Frederick E. Dewey et al
- 雑誌名
- SCIENCE
- 号、発行年
- 23 December 2016, VOL 354
研究者経歴
1966年、大阪府生まれ。1991年に大阪大学医学部卒業。1999年に同大学医学部大学院博士課程(医学)修了。外科医としての勤務を経て、1999~2003年、米国オハイオ州立大学研究員。2003~2008年、東京大学医科学研究所ヒトゲノム解析センター助手、准教授。2008年より現職。AMED 「ゲノム創薬基盤推進研究事業(旧・ゲノム医療実用化推進研究事業)」、「臨床ゲノム情報統合データベース整備事業」、「オーダーメイド医療の実現プログラム」それぞれのプログラムオフィサー(PO)を務める。
関連リンク
掲載日 平成29年11月8日
最終更新日 令和2年3月30日