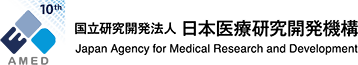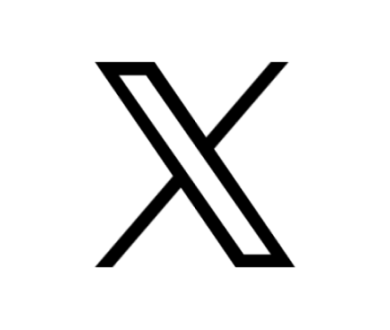アーカイブ インタビュー No.6「研究者として挑む小児白血病との闘い ~扉は "新しい人、新しい考え方"との出会いで開かれる」

東京医科歯科大学 名誉教授
臨床医と研究者の間で、小児の希少疾患、特に小児白血病/小児がんの疾患メカニズム解明のために今何が必要かを One for all, All for one の精神で探求する水谷先生。「ゲノム医療の目覚ましい進歩に驚いています。この時代にめぐり会えたことは幸せ」と語る水谷先生が抱く“ゲノム医療に寄せる期待と課題”について、お話を伺いました。
患者を助けられない挫折感
研究で「医」の活路を見出そうとした若き日々
― 臨床医でいらっしゃった水谷先生。研究者を志す"きっかけ"をお聞かせください。
若い頃は、主に白血病やがんの子どもたちを診療しました。この病の子どもさんを何人も看取り、深い挫折感を味わったことは、研究者の道を選ぶ大きなモチベーションにつながりました。このまま対処療法を繰り返す、同じことをやっていたのではだめだ、と。
海外の論文などから、サイエンスが臨床の中に入り込んできている状況を知り、1984年から1986年までイギリスに留学をしたことが研究者生活の始まりです。私のように、臨床から基礎研究の重要性を感じ、研究の世界に入っていく臨床医は少なからずいるでしょう。そのままずっと基礎研究をやっていく人、あるいは、基礎研究を経験した後また臨床に戻って、基礎研究の視点から臨床を見直そうとする人、両方とも必要です。海外では、基礎一本やりで進まれる理学系、薬学系とか農学系のいわゆるPh.Dが、臨床のことを医者以上によく理解していることが度々あり、驚きました。留学中の指導者であるメル・グリーブス(Mel Greaves)先生も小児白血病をテーマとするPh.Dで、臨床にも詳しかった。
AMEDのプログラムスーパーバイザー(PS)をお引き受けした際、私のような者でいいのだろうかという思いがありましたが、今は、臨床と基礎研究の両方に携わった経験がこれからのゲノム医療を考える場面において貴重なのかもしれないと思い、この経験が生かせればと願っています。

― なぜ、ゲノム医療に取り組もうと思われたのでしょうか?
1980年頃にnon-T、non-Bタイプのリンパ性白血病で免疫グロブリン遺伝子の再構成が明らかにされました。この研究が世界的にもゲノム診断やゲノム医療の最初の扉を開いたのではないかと思います。それまで、表面マーカーでリンパ性白血病は主にT細胞性のALL、B細胞性のALL、表面マーカーで特徴を示さない non-T、non-Bと呼ばれるタイプの3種類に分類さていました。この中のnon-T、non-Bタイプが実はどういう白血病なのかわからないという時代でした。しかし、ゲノムを調べたところ免疫グロブリン遺伝子の再構成が始まっていることが発見され、これらはほとんどがB細胞の初期段階のものであるということが初めてわかったのです。つまり、ゲノムレベルでnon-T、non-Bタイプのリンパ性白血病の帰属が解明され、細胞分化の性格を診断できるようになったのです。正確な診断ができて、初めて、「この類いの白血病は予後がいいのか、悪いのか」という議論ができるようになります。
そうこうするうちに、ある種の白血病では、特定の染色体がちぎれて断片同士が相互にくっつく現象(相互転座)が高い頻度で起こっていることがわかりました。染色体の切断点がクローニングされ、細胞遺伝学的診断がゲノムのレベルで可能になり、その情報と臨床データの特徴が調べられると両者がよく相関していた。これにより、白血病のゲノムの診断が、臨床においても重要であることがわかりました。この後、NGS(Next Generation Sequencer、次世代シークエンサー)の登場によって、特定の臨床的特徴を持った白血病のさらに詳細なゲノム異常が明らかになってきました。
― そういった時代だったのですね。
このような遺伝子変化が治療に直結することは長年ありませんでした。しかし、その後ゲノム医療研究が治療に結びつく大きな研究成果が出現しました。それは、慢性骨髄性白血病を舞台に展開されました。慢性骨髄性白血病腕は9番と22番の染色体の相互転座の結果生じる「フィラデルフィア染色体」が、95%の症例で関与することが1959年に発見されていましたが、その染色体が一体どういうことを意味するのかはずっと謎でした。しかし、染色体の転座点のクローニングに成功したことで、BCRとABLという2つの遺伝子がリコンビネーションを起こして、最終的にBCR-ABLという融合たんぱくを作っていることが1983年に解明されたのです。このたんぱくは細胞をがん化させる活性を持っており、その後、たんぱく構造を解析することによって、その阻害剤である新薬が発明され、今や、慢性骨髄性白血病によって命を落とされる方はほとんどいなくなりました。この阻害剤は分子標的薬のはしりといえる治療薬です。それまでは治療で一時期によくなっても、やがてBlastic Crisisという、いわゆる急性白血病のパターンで再発してしまい、骨髄移植等で一部の患者さんしか救済できなかったのですから、時代が大きく変わったということです。これがきっかけとなって同じような薬をいろいろながんの領域の中でも見出していこうとなった。そういう意味では、白血病の研究はゲノム診断そしてゲノム医療の突破口を切り開いた1つのモデルケースだろうと思います。
― この三十数年間のゲノム領域解明に関わる進歩は目覚ましいものですが、水谷先生からご覧になって、印象に残っている重要な要素やイノベーションはありますか?
小児ということで、ちょっと話が狭まってしまいますけれども、染色体転座のゲノム解析から小児白血病の発症時期が胎児期にあることを、1993年に英国のGreaves博士らが解明したことです。子供の白血病が生後始まるのか、生前つまり胎児期に始まるのかは、長年の謎でした。一方、長い臨床的観察の中で、一卵性双生児の片方が、例えば1歳未満で白血病になった場合、もう片方も白血病になる確率が非常に高いことがわかっていましたが、彼らは一卵性双生児の2人に発生した白血病が全く違うオリジンなのか、あるいは共通のオリジンなのかを染色体の転座点の遺伝子解析で明らかにしました。結果的に一卵性双生児の同胞間の白血病は全く同じものでした。そうすると、白血病化に向けた最初のイベントは生まれてから起こったことではなく、生まれる前(胎児期)に起こっていたということになります。双生児のどちらかに発生した白血病のクローンを2人が共有してしまったために2人が同じタイプの白血病になったことが遺伝子レベルで裏付けられたのです。その後さらに研究が進んで、1歳以上の小児の白血病において、その子の新生児期に採取され、保存されていたろ紙血(ガスリー血)を使って、その中に白血病のクローンが存在しているかをPCR(polymerase chain reaction、ポリメラーゼ連鎖反応)で追跡しています。その結果、15歳ぐらいまでの白血病の子の、白血病の最初のヒットは胎児期にあると推測されるに至っています。胎児期に最初のヒットを受け、その後何段階かの追加的ヒットを受けて白血病が発症するという推定が可能になったわけです。採取後数年で廃棄される運命にあるガスリー血を保管することの重要性が同時に証明されたことになります。
― 今まで臨床医が経験値として持っていた病気の症例や症状が、基礎研究によりクリアに解明され、さらに次の研究につながるということでしょうか?
そうですね。この研究をきっかけに、他のタイプの白血病についても胎児期に始まっていることが明らかにされ、遺伝子解析による細かい分類をベースに原因を胎児期の環境にまで遡ろうとする研究が国際協力の中で進められるようになっています。いわゆる分子疫学の国際共同研究です。創薬・治療には直結していませんが予防策を講じるうえで貢献する可能性が高いと思われます。
― 臨床医側の経験値があるからこそある程度めどをつけて研究できるところと、臨床医の経験がなくともスクリーニング結果でリーチしたものと、どちらも非常に重要なのかなとお話を伺って思いました。その辺りのバランスも、研究推進の要因でしょうか?
研究者同士、言い換えれば、同じものを見ても異なった見方で考える者同士の出会い・融合・共同作業が新たな成果の扉を開くのではないかと思います。私見ですが、海外ではそういう意味での連携プレーがうまいですね。お互いに競合しながら仲よくやってwin-winの関係を築いているようです。研究支援体制の違いによるのかもしれませんけれどもね。限られた研究資金をめぐって自分たちのテリトリーを守りたいがために過度な競争に走る。そのような要因がひょっとしたら日本の背景にあるかもしれません。
希少疾患だからこそ症例登録の一元化、研究基盤の共有、診断システム中央化を整備
そして、中央バンキングシステムを未来のために

― 先ほどヒトの病気のためにさまざまな考え方の人たちが集まることに価値があるとおっしゃいました。しかし、こと日本では、チーム体制で希少疾患という病気、そして患者に向かい合うことはできているのでしょうか?
小児がんは希少疾患の代表的存在なので、ここで小児がんへの取り組みである特定非営利法人・日本小児がん研究グループ(JCCG: Japan Children's Cancer Group)のことを紹介しましょう。一般的に発症数の多いがんであれば、大学・病院ごとに患者をある程度の数集めて、集めたサンプルの中でデータを出して論文化できるのですけれど、小児がんは発症数が日本全体で年間2,500人前後でいわゆる希少がんの範疇に入ります(希少がんの定義:人口10万人あたり6例以下)。これは大学・病院ごとでは年間5例ほどしか経験できないレベル。当然医師の経験値も低く、サンプルを集めることも難しいのです。そこで小児がんを扱う施設の人たちが研究グループを構成して共同研究というかたちで治療成績を出すことにしました。その結果、1969年以来日本各地に小児白血病や小児がんの臨床研究グループが続々と誕生し、それぞれのグループが競い合い、経験を積んでより良いデータを出そうと努力してきました。しかし、欧米ではさらにそうした取り組みが先行していて、規模も大きく、何千例という症例を集めてデータを出してきました。そうなると日本のように小グループに分散していては到底追いつかない。そこで私たちは2014年12月にJCCGを結成してオールジャパンで小児がんに取り組む体制を構築しました。現在会員施設が198施設になり、全日本に広がっています。その中には小児がん拠点病院や小児がん学会専門研修施設が全て参加しています。
また、小児がんは全体の数が少ない上に、多様な種類のがんがあります。そうなると小児がんの病理診断の専門家が少ないために、どこの病院に行くかによって診断名が異なるという危険性があります。それを避けるためにJCCGでは中央病理診断という仕組みを作りました。小児がん病理分野のエキスパートにネット上で集まってもらい、同じ標本を見て統一的な診断をしてもらう。それに免疫学的手法や遺伝子解析による分類を加え、最終的に治療研究グループでどういう治療法がいいかということを考えます。こうやって3~5年ごとにプロトコルを改訂していきます。データセンター機能の強化により症例登録を一元化し、診断システムの中央化など研究基盤を共有・整備してきたわけです。これにより治療成績は年ごとに改善しています。治療の難しい疾患群の特徴が明らかになり、新たな治療戦略の目標が立てられるわけです。言うなれば日本全体を1つのバーチャルな小児病院にし立て上げ、診断/治療戦略を立てようというわけです。これは国際共同研究へのイニシアチブを取る上でも有利になります。
このように日本の小児がんを統一的に診断、分類して、がんの種類ごとに臨床試験を実施し、治療法を検証することを主眼においていますが、それをゲノム情報とどう結びつけていくかというところが今後の大きな課題です。生体試料を個々の施設でバンキングをしていると、責任者が交代するたびに試料が散逸してしまいます。そこでJCCGでは中央で診断のついたケースを、これまではバイオバンク・ジャパン(BBJ)で保管してきました。特に稀少疾患に関しては、そういった中央バンキングのような仕組みを作って、きちんとした形で管理するのが一番望ましい。臨床データと中央診断の仕組みがうまく連携し、生体試料バンクが整備されることで、初めて来たるべきゲノム医療が進歩していくだろうと思うのです。このような生体試料は人類の貴重な遺産ともいうべきいわゆる「レガシーサンプル」であって、長い年月をかけて蓄積されていくものです。こういう基盤がしっかりしていれば、将来全ゲノム解析などによって、個々のがんの特性やその詳細が明らかになり、新たな治療法が発見されるかもしれない。年間の症例数は少なくても、歴史的に蓄積できればいわゆるビッグデータ化する可能性が高まり、その解析が別の切り口での治療法開発につながると期待されます。これは将来の子どもたちのための財産にもなるはずなのですが、現状ではそういう基盤づくりのための経費捻出が難しい状況です。

― まさにそうですね。生体試料のバンク化は、ゲノム解析への大きな道をつけることになる。しかし、試料を"貯める"というこれまでとは違うインフラが必要になり、かつイニシャルコストだけではなくてランニングという、ある意味長期的にコストが必要になってくる可能性があります。この部分は短期間の研究費では賄えないものです。そのような背景の中、JCCGの取り組みを国主導でなく始められる・維持されるに至った経緯をお聞かせください。
小児がんの疾患克服に向けて先進的取り組みが求められています。数は少なくても患者は全国いたるところで発生します。このような病気に取り組むために厚生労働省では集約化というキーワードで拠点病院に集約することを当初考えました。一方、私は患者や家族の負担を考えると集約化には限界があります。必要なのは"がん治療に取り組む病院のネットワーク化とそれを支える臨床研究の基盤整備"と考えてきました。ですから、JCCGは当初から全国を統一する研究基盤の整備を目指しています。
生体試料の処理、DNA抽出やその保管を巡って国の支援を求めてきましたが、思うように得られなかった、というのが悲しい現実です。そのために患者会をはじめ、各方面からの支援も欠かせない状況なのです。現在、JCCGは先に述べたような規模に拡大し、日本で唯一、最大の、小児がんに特化した研究グループとなりました。しかし昨年、バンキングに必要なDNAの抽出費用を捻出できない状況が起きました。1検体単位当たり5,000円かかりますから、もし2,000件抽出したなら1,000万円が必要になります。昨年は幸い個人の篤志家の方が高額な寄付をしてくださったことで窮地をしのぎましたが、毎年このような支援がいただけるとは限らないのが辛いところです。
― どう国民の皆さまに周知、理解、コンセンサス、支援を得るかですね。
やはり、現場の先端的で地道な試みとそれを維持するための仕組み、"この部分をどうしても支援してもらいたいのだ"ということがわかるメッセージを発信することが重要だと思っています。それは研究者が本来的に取り組むべき仕事かという点ではかなり疑問があるのですけれど、何もしないと資金が不足し、研究グループとして立ち行かなくなります。医師、研究者が集まって国民の皆さまのお力を借りながら慣れない寄付活動を進めています。
海外と比して日本に足りないのは患者や市民団体との協力、国や国民が一緒になって研究を支援する発想が乏しいとも言えます。この部分が大きく成長すれば、将来的にはその資金で中央診断や中央生体試料バンクなどの研究基盤を整備でき、若手研究者を育成することもできるでしょう。医療者側も国民にわかりやすい説明をする義務があると思っています。
参考のための事例を紹介しますが、イギリスには、白血病で子どもを亡くした親御さんが1960年に設立した英国白血病研究基金という団体がありました。国民の寄付によって年間何十億という資金を集めて研究プロジェクトをサポートする仕組みができていました。日本でも25年前に同様な試みを公益信託日本白血病研究基金として私たち有志が数名で始めています。皆さまから多大なご支援や寄付をいただいていますが苦労は尽きません。
もっと自己肯定していい
可能性を信じれば、心を開いて対応してくれる人が現れる
― 若手研究者、または、小児医療に取り組む医師に伝えたいことはありますか?
臨床の生体試料で基礎的・科学的データが得られる良い時代です。しかし、ビッグデータを得るには多くの仲間との協力関係、信頼関係が必要です。これからは研究者にしても臨床医にしても人間として"仲間や病者と共に生きる姿勢"がより一層求められます。日本人は内向き志向で自己肯定感乏しい人種とよく言われます。けれど、もっと自分を肯定し、相手も肯定していく中で心を開いて共に協力できれば新たな地平が切り開かれるはずです。どうしてもアカデミアにいると、自分の世界に閉じこもりがちですが、そこは一歩乗り越えて、皆さんもっと解放的で前向きであるべきです。
少し話は逸れますが、今、私は大学を定年退職後、子どもの発達障害児の施設でもお手伝いをさせていただいています。診療を求めていらっしゃるお母さんたちに思うのですが、子どもに対する見方が概して悲観的です。「ほかの子に比べて同じレベルのことができない」「標準的でない」と悩んでいる方が多くて。そういう方に対して私は、親が子どもの可能性を信じることが何より大事だと伝えています。子育てに近道はありません。遠回りのことはあっても、愛され、信じてもらえることによって、子どもは安心して成長する機会を見出すことができる。子どもの側に「自分は愛されている、信じられている」と思える豊かな親子関係が育つ社会の中にあってこそ、医療や科学をはじめ、さまざまな分野で活躍する優れた人材が生まれるのではないかと思うのです。
(取材日:2018年6月29日、聞き手:一般社団法人知識流動システム研究所 代表理事 西村 由希子)
インタビュー映像
推薦論文
- タイトル
- Nusinersen versus Sham Control in Infantile-Onset Spinal Muscular Atrophy
- 著者名
- Richard S. Finkel, M.D., Eugenio Mercuri, M.D., Ph.D., Basil T. Darras, M.D., Anne M. Connolly, M.D., et al.,
- 雑誌名
- The New England Journal of Medicine
- 号、発行年
- 377(18):1723-1732. 2017
- 推薦趣旨
- 脊髄性筋萎縮症に対し、新しい発想に基づく核酸医薬であるNusinersenが画期的効果を発揮することが明らかにされた論文です。これまで諦められていた子どもが歩けるようになったのです。本疾患は先天性小児難病であると同時に希少疾患であるため、国際共同研究により多数例での治験が必要でした。小児疾患を克服するために国内的/国際的共同研究体制が求めらていることを示しています。
研究者経歴
1948年、京都府生まれ。1974年に東京大学医学部卒業。医学博士(東京大学)。東京大学病院等で小児科医を務め、35歳の時、2年間のイギリス留学をきっかけに研究者への道を歩む。帰国後は、国立小児病院(現在の国立成育医療研究センター) ウイルス研究室長として小児がんの基礎研究に携わった。2000年に東京医科歯科大学学院発生発達病態学・小児科学 教授、同大学副学長(産学連携本部長)を経て、2014年に定年退職。専門は小児がん、白血病。現在東京医科歯科大学名誉教授。AMED「ゲノム医療実用化推進研究事業」プログラムスーパーバイザー(PS)。JCCG 初代理事長。公益信託日本白血病研究基金の創設者でもある。
掲載日 平成30年8月1日
最終更新日 令和2年3月30日