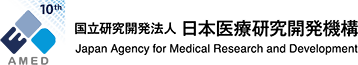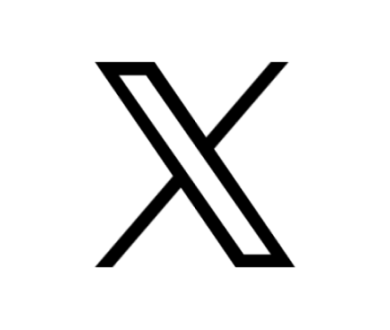アーカイブ インタビュー No.8「エピゲノムからみたゲノム医療」
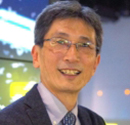
九州大学生体防御医学研究所 教授、同大学 副学長および高等研究院長
エピゲノム研究の第一人者であり、内科医を経て30年以上にわたり、エピジェネティクスの機構と疾患の関連を追い続けてきた佐々木先生。「ゲノムでは説明のつかないこと」をどのように解明し、治療につなげていくことができるのか。そして、今後さらなる突破口を見出す上で“必要なこと”について、お話を伺いました。
エピゲノムがもたらす新たな視点
― 佐々木先生はエピジェネティクス*1)の専門家として、ゲノム医療実現推進プラットフォーム事業のプログラムオフィサー(PO)に就任されています。どのような思いで引き受けられたのでしょうか。
私はゲノム医療の専門家ではないので、話が来たときには驚きましたが、ゲノム医療を推進するプログラムスーパーバイザー(PS)、POの先生方から「ゲノム医療にはエピジェネティクスの視点が必要」という声が上がったと聞いています。
エピジェネティクスは、個体発生の過程で、親から受け継いだ塩基配列を維持しつつ、遺伝子発現を変化させるゲノムの調節機構のことです。さまざまな生命現象や病気を解明する鍵を握ると考えられています。
エピジェネティクスは環境の影響を遺伝子の働きに変換する仕組みでもあります。ほとんどの疾患には「遺伝」と「環境」の両方が関わっていますが、ゲノムだけで説明できないこと、これまで環境要因としてくくられていたことが、エピジェネティクスの視点を導入することで上手くつなげ説明できるのです。
ゲノム医療実現推進プラットフォーム事業では、疾患の発症に遺伝子多型などのゲノム情報や、ライフスタイルや行動といった環境要因がどのように影響を及ぼしているかを解明して、最終的には個別化医療につなげることを目指しています。
私は内科医として医学の世界に入ったので、エピジェネティクスの異常が関わる病気に大いに興味があります。マウスを使った基本的なメカニズムの研究がメインですが、臨床医の先生方、特に小児科や産婦人科の方々と連携する機会が多いです。エピゲノム*1)の視点をゲノム医療に取り入れることで、何か新しい発見につながればと考えています。
― 佐々木先生はエピジェネティクスの重要性に早くから着目され、これまでにメカニズムの解明から病因の解明、さらに治療法の開発など幅広い貢献をされています。エピジェネティクスに対する近年の関心の高まり、手ごたえについてはいかがですか。
「エピジェネティクス」という言葉自体は1950年代からありましたが、その使用はごく一部の遺伝学者や発生学者に限られていました。1980年代以降、哺乳類でX染色体の不活性化*2)やゲノム刷り込み(ゲノムインプリンティング)*3)のメカニズムが明らかになってくると、徐々にエピジェネティクスへの注目度も高まっていきました。
私自身は、大学院生だった35年ほど前、ある遺伝病(家族性アミロイドポリニューロパチー)の研究をしていたことが契機になり、エピジェネティクスの研究に足を踏み入れました。この遺伝病の原因遺伝子をマウスに導入して、疾患モデルを作製したところ、ゲノム刷り込みが見つかり、ここからエピジェネティクスのメカニズムについて詳しく調べ始めました*3)。
これが1980年代後半~90年代初めのことで、当時は国内を見渡しても、同じ分野の研究者は数えるほどしかいませんでした。今では神経科学や発生学、がん研究の分野など、さまざまな分野から研究者が参入していて、当時からすると夢のようです。特に2003年のヒトゲノム計画の完了をもって、ポストゲノム時代に突入すると、遺伝子の発現を司るエピジェネティクスに対する関心もますます高まっていきました。
エピジェネティクスの異常と疾患

― これまでに疾患との関係はどの程度、明らかになってきているのでしょうか。
がんについては、ここ20年ぐらいで随分明らかになりました。例えば、突然変異や染色体欠失でがん抑制遺伝子が機能しなくなるとがんになるわけですが、がん抑制遺伝子の遺伝情報自体に変化がなくても、異常なDNAのメチル化により、がん抑制遺伝子が不活化されることが、がんの原因になるのです。
エピジェネティックな調節は主にゲノムの化学的な修飾や構造変換によって行われています。DNAのメチル化は、遺伝子のスイッチをオフにする目印であり、その遺伝子を不活性化します。これは、たった1つの受精卵が、種々の細胞系譜に分化していく上で不可欠な仕組みです。同じゲノム情報をもとにしながら、使う遺伝子・使わない遺伝子を制御することで、皮膚なら皮膚、肝臓なら肝臓、とそれぞれの細胞に固有なエピゲノムを確立していくわけです。
しかし、誤ってがん抑制遺伝子をメチル化してしまうと、発がんにつながります。例えば、ピロリ菌感染が引き起こす慢性炎症による胃がん、長期的な喫煙による食道がんは、DNAのメチル化異常が発生リスクを高めていると考えられています。まだ全貌が解明されているわけではありませんが、他にも白血病や大腸がんなどさまざまながんでエピジェネティクス異常の関与が報告されています。
― エピジェネティクスの異常が原因だと判明した場合、治療の可能性もありますか。
ゲノムを変えるのは遺伝子治療でもしない限り不可能ですが、エピゲノムは薬や生活習慣をコントロールすることで正常化できる可能性があります。
すでに、ある種の白血病やがんに対しては、DNAの脱メチル化剤や、ヒストンタンパク質の脱アセチル化酵素の阻害剤が用いられていて、効果が示されています。エピジェネティクスの実体は、メチル化、アセチル化といった化学修飾であり、それは生体内の酵素によって触媒されます。つまり、その酵素を阻害もしくは活性化する薬があれば良いわけです。
ただし、治療標的となる酵素が作用する遺伝子は1つとは限らず、同時に何十、何百の他の遺伝子に影響を及ぼすことも考えられるので、副作用のリスクについては十分に考慮する必要があります。
― がん以外にも、エピジェネティクスの関与が疑われる疾患はありますか。
当然ながらエピジェネティクス機構に根本的に関わる遺伝子、例えばDNAメチル化酵素の遺伝子に変異があると遺伝病になることが知られています。例えば、DNAメチル化酵素がうまくはたらかず起こる病気の1つに、「ICF(immunodeficiency, centromeric instability, facial anomaly)症候群」という先天性の免疫不全疾患があります。
また、妊娠中の母体の栄養状態が悪いと、胎児の将来的な肥満や糖尿病のリスクが高まることは、すでに疫学的な調査から明らかになっています。発生発達の過程で暴露された環境の影響が、何十年も経った後の健康や病気に影響することには、おそらくエピジェネティクスが関与しているだろうということで、世界的に、そして爆発的に研究が進んでいます。
その他にも最近、報告が出始めているものとしては、統合失調症などの精神・神経疾患、アレルギーや自己免疫疾患、腎臓・心臓疾患などが挙げられます。がんとエピゲノムの研究に比べると日が浅いため、治療につながったものはまだあまりありません。まずは疾患メカニズムの解明を進めていくことが今後の課題になると思います。
― ゲノム医療との結びつきについては、いつ頃から指摘されているのでしょうか。
ゲノムとエピゲノムの両面から疾患を捉えようとする動きが実際に出てきたのは、がんを除けば10年ほど前からではないでしょうか。
がんは手術で組織を採れるので、サンプルの入手が容易です。初期から進展したがんまで、段階的にサンプルを比較することで、どのような順番でどの遺伝子にメチル化が入るのか、変異が入るのか、その過程を追うことができるので、がんのエピジェネティクスの異常については相当詳しく分かってきています。
ただ、臨床のサンプルをエピゲノム解析すれば、必ずしも病気との関係が明らかになるわけではありません。エピジェネティクス、エピゲノムで難しいのは、まず正常なパターンを決めなければならない点です。同じ個体ならゲノムはどの細胞を見ても同じですが、エピゲノムは、細胞の種類によって違います。まず、それぞれの細胞の正常状態を見極めないと、発症時との比較ができないのです。
そこで、日本も参加している「国際ヒトエピゲノムコンソーシアム」*4)では、正常状態のエピゲノムを決めて、世界中の医師・研究者が利用できるデータベースとして、高精度のヒトエピゲノム地図をつくることを目指しています。
また、母体の栄養状態と子どもの肥満との関連について例に挙げましたが、では実際にどの細胞のエピゲノムが変化したのかというと、脂肪細胞や筋肉細胞かもしれないし、腸や肝臓の細胞かもしれないし、摂食行動を調節する脳細胞かもしれません。どの細胞に着目すべきか見当をつけるところから研究が始まるので、疾患との関係を突きとめるのは、なかなか大変なことです。
研究推進に必要なコト・モノ・ヒト

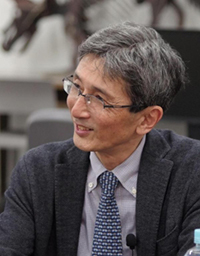
― エピゲノム特有の難しさがある中でも、ここ数年で研究が加速している理由としては何が挙げられますか。
NGS(Next Generation Sequencer、次世代シーケンサー)の登場で、解析速度が飛躍的に向上して、コストも下がってきたことが大きいです。それと同時に、ビックデータを扱うバイオインフォマティクスも不可欠で、その両輪ですね。ここ十数年の進展は目ざましいです。
また、エピジェネティクスは化学修飾なので、化学的な検出法や、抗体を用いた検出法も重要ですし、モデル生物の作製においてはゲノム編集の登場で、以前とは段違いに効率が高まりました。やはり研究の発展にはテクノロジーの進歩が欠かせません。
今、盛んにAI(人工知能)の活用が叫ばれていますが、ゲノム医療においても、今後は情報の活用が鍵になってくるでしょう。山のように蓄積していく情報をいかに統合、取捨選択し、医療の現場で役立てるのか。精密医療も精密になるほどコストの問題が出てくるでしょうし、情報の利活用について真剣に考える時が来ていると思います。
― 佐々木先生のご研究でも、情報科学を駆使されていますよね。平成30年度の特別推進研究「多階層オミックスによる卵子の発生能制御分子ネットワークの解明」では、マウスを対象とした逆遺伝学のアプローチと共に、収集されたエピゲノムデータに機械学習・数理モデルを適用されています。
私たちの研究では、次世代へ伝達するエピゲノム変化を予測するモデルを構築することで、将来的には、疾患感受性関連のエピゲノム変化の伝達機能の解明や、これまで原因不明だった不妊・流産の解明や、生殖医療の改善につなげることを目指しています。
これまでの常識では、エピゲノムは基本的には一世代限りでリセットされて、次世代に受け継がれるものではないと考えられてきましたが、どうも次世代に影響する可能性がありそうだということも最近明らかになってきました。
ある意味、生物学で否定されている、獲得形質が遺伝するといったようなことが、もしかするとエピジェネティクスではあり得るかもしれないのです。実際に、植物では、DNAのメチル化パターンが世代を越えて伝わっていくことが明らかになっているので、ヒトを含めて、哺乳類でもないとは言い切れません。
― 今後さらに研究を進める上で、注力したい点は何でしょうか。
基礎的なことはマウスで研究できますが、最終的にヒト細胞でエピゲノムを調べる手段は限られています。その壁を越えて、再現性のあるデータを得るには、患者さんになるべく負担をかけずに、例えば少量の採血でエピジェネティクスの異常を調べる手法を開発するといった工夫が必要になってくると思います。
また、例えば糖尿病の患者と健常者からそれぞれiPS細胞を作製し、そこから膵臓を再現して比較するといったことも考えられます。エピジェネティクスは再生医療との接点が大きい分野です。iPS細胞の作製では「山中ファクター」を用いて細胞を初期化しますが、これはエピゲノムの時計を巻き戻しているわけです。iPS細胞から目的の細胞に分化誘導するのにも、当然エピジェネティクスが関わるので、こうしたところでも私たちの研究が役立てば良いなと思っています。
― POを引き受けられたことは、研究を進める上でもプラスとなっていますか。
はい。従来から距離が近かった小児科や産婦人科の先生に加えて、糖尿病や高血圧、腎臓病など、いわゆるコモンディジーズの研究をされている先生方とも知り合いになりました。さまざまな分野の先生方がエピジェネティクスに関心をお持ちであると実感しています。
確かにPOの仕事は、自分の分野に直結する仕事だけではないので大変ですが、その分、得るものも大きいです。専門外のことに目を向けておくことは、やがて行き詰まった時に突破口を見出す上で必ず役に立つはずです。
学生たちにもよく言っていることなのですが、科学者・研究者は、新しいものを創っていくことが仕事です。自分の専門分野を勉強するのは当たり前で、むしろ一見関係ないと思うことを、貪欲に吸収していくことが、新たなアイディアやモチベーションにもつながります。
― 異分野と融合するための"余白"をどれだけ持てるかということですね。
むしろ、そういうところにしかブレークスルーはないのかもしれません。制度や組織も細分化しすぎないことが大切だと思います。お互い何をしているのか見えるようにしておかないと、自分の領域外のことは知りません、分かりませんとなってしまいます。
世の中を前に進めるには、シンプルなやり方が良いように思います。ゲノムプロジェクトの時、多くの研究者は染色体ごとに、端から順にパーツを埋めようとしましたが、結局は、ショットガン法で適当に切断した断片をシーケンスし、そのデータをつなぎ合わせることで配列が決まりました。多少の無駄はあるかもしれませんが、シンプルな方が結局は効率がいい。こうした発想の転換は非常に重要です。NGSもこうした発想がなければ生まれなかったと思います。
目標を設定する際にも、具体的に絞り込みすぎたり、狭い範囲で捉えたりしていても、革新的な研究成果はなかなか生まれてこないと思います。応用を支えるのはやはり基礎研究であり、その裾野は常に広くしておくべきです。
― 個人も組織も、広い視野と柔軟な姿勢が大切だということですね。最後にゲノム医療に関わる若手の医師や研究者に向けてメッセージをお願いします。
若い人には、とにかく自分の専門外のことをいろいろ見ると同時に、日本を飛び出して世界を見てほしいと思います。最近は留学する学生が減っていますが、その背景には日本が豊かになり「わざわざ留学しなくても」という風潮や、大学の先生方も業務に追われて、海外の学会に参加するのが難しくなっている現状があるように感じるのです。
他方、中国の勢いはすごい。私は中国・蘇州のCold Spring Harbor Asia Conferenceのオーガナイザーをしていますが、中国の学生はひっきりなしに英語で質問してきます。中国では、海外の一流大学で教授をしている研究者を呼び戻したり、国内の大学にもポストを与えて両国で活躍できるようにしたりしています。身近にこういうロールモデルがあると、自分も頑張ればああいう研究者になれると思うのでしょうね、学生の目の輝きが違います。(写真2)
すでに大学ランキングや高引用論文の数等からみても中国は日本を超えています。日本はもうアジアの盟主ではない。とはいえ、日本は諸外国からまだまだ尊敬されていますし、仕事ぶりに対する信頼も厚いです。自信をなくす必要はありません。ただ、内向的なままでは、いずれ世界に取り残されてしまうでしょう。ぜひ外にも目を向けて、いろいろなことを積極的に吸収してください。もちろん、日本国内でのディスカッションも重要です。2019年の第43回日本分子生物学会年会(会場:福岡県福岡市)でも、若手の方々による活発な研究成果発表を期待しています。
(取材日:2019年1月31日、聞き手・インタビュー構成:一般社団法人知識流動システム研究所 フェロー 本田 隆之・堀川晃菜)
用語解説
- *1)エピジェネティクス、エピゲノム
- DNAの塩基配列を変えることなく、遺伝子のはたらきを決めるしくみをエピジェネティクスと呼び、その情報の集まりをがエピゲノムという。例えば、三毛猫の毛の模様やアサガオの花の絞り模様もエピゲノムで決まる。
疾患との関連についてはこちら:エピゲノムと疾患 - *2)X染色体の不活性化
- 哺乳類のオスはXY、メスはXXの性染色体構成をもち、メスはX染色体の遺伝子がオスの2倍ある。雌雄間で遺伝子量の差を是正するため、哺乳類のメスは2本あるX染色体の1本を不活性化する。その際、不活性化されるX染色体は2本のX染色体から基本的にはランダムに選ばれる。三毛猫(すべてメス)の茶と黒を決める遺伝子がX染色体にあり、不活性化の起こり方で模様が決まることが知られている。
- *3)ゲノム刷り込み
- 哺乳類の精子や卵子の形成過程において、何らかの形で遺伝子に「しるし」あるいは「記憶」が刷り込まれ、その「しるし」に従って子での遺伝子発現が生じることをゲノム刷り込み(ゲノムインプリンティング)という。インプリティング遺伝子には、父親から受け継いだ染色体でしかはたらかない遺伝子PEG(Paternally expressed genes)と母親由来のみはたらくMEG(Maternally expressed gene)がある。佐々木先生は、精子・卵子における刷り込みの実態が DNA メチル化であることを証明するなど、生殖細胞におけるゲノム刷り込みの確立機構の解明に取り組んでいる。
- *4)国際ヒトエピゲノムコンソーシアム
- International Human Epigenome Consortium(IHEC:通称アイヘック)。さまざまな病気や生命現象に関わるヒトエピゲノムの情報を世界各国の研究者で協調・分担して解析し、高精度のヒトエピゲノム地図をつくることを目的に、2010年に始動した国際的な研究組織。日本では、2014年度まで 科学技術振興機構(JST)の戦略的創造研究推進事業(CREST)が、2015年度からは研究領域を継承した日本医療研究開発機構(AMED)のCRESTがIHECを支援している。
詳細はこちら:国際ヒトエピゲノムコンソーシアム、IHEC
インタビュー映像
推薦論文
- タイトル
- Integrative analysis of 111 reference human epigenomes
- 著者名
- Roadmap Epigenomics Consortium
- 雑誌名
- Nature
- 号、発行年
- 518, 317-330 (2015年)
- タイトル
- The International Human Epigenome Consortium: A Blueprint for Scientific Collaboration and Discovery
- 著者名
- Stunnenberg, H.G., The International Human Epigenome Consortium, Hirst, M.
- 雑誌名
- Cell
- 号、発行年
- Volume 167, Issue 7, 15 December 2016
研究者経歴
福岡県生まれ。1982年に九州大学医学部を卒業。同年に九州大学医学部第一内科 研修医。1983年に九州大学大学院医学研究科へ入学し、1987年に修了(医学博士)。 同年から同大学遺伝情報実験施設で助手を務めた後、1990年に英国AFRC動物生理学遺伝学研究所、1992年にはCambridge大学Wellcome/CRC研究所のそれぞれ海外リサーチフェロー。 1993年に九州大学遺伝情報実験施設 助教授、1998年に国立遺伝学研究所人類遺伝研究部門 教授。2010年に九州大学生体防御医学研究所エピゲノム学分野 教授に就任、同大学の主幹教授、生体防御医学研究所 所長を経て、現職。
掲載日 平成31年3月15日
最終更新日 令和2年3月30日