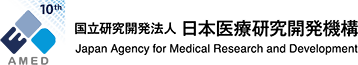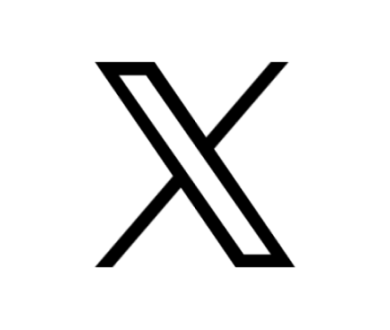HFSP 30周年記念スペシャルインタビュー
HFSP 30周年記念インタビュー ~これからの基礎研究と研究費を考える~
いま医学・生命科学研究の領域では、応用志向の強まりと基礎研究費の縮小に対する危機感が叫ばれています。一方で世界を見渡せば、HFSP(Human Frontier Science Program)という「純粋基礎研究のみ」を追求する大型の国際研究助成が、間もなく30年の歴史を数えようとしています。HFSPは15国・極の共同出資による事業で、1989年に日本の旗振りで始まったものです。大きく分けてグラント(3年で1億円を超える研究費)・フェローシップ(留学助成)・CDA(独立支援)の3つがあり、成果論文が国際平均の3倍の引用度を示すなど、その「目利き」が国際的に認められています。
今回、2019年にHFSP 30周年を控えるこの機会に、かつてHFSPグラントを受賞されたフロントランナーの先生方に、基礎研究の“フロンティア”に挑戦すること、そのための研究費を獲得する戦略について、あらためてお語りいただきました。研究者の自己実現に役立つヒントが満載ですので、ぜひご一読ください。

- <インタビュー>
- 田中啓二 先生 (東京都医学総合研究所)
- <HFSPグラント受賞テーマ>
- プロテアソームの構造と機能(1995年)
- <プロフィール>
- 1949年 徳島県生まれ。徳島大学医学部栄養学科卒業後、米国ハーバード大学医学部研究員、徳島大学酵素科学研究センター助教授、東京都臨床医学総合研究所部長・副所長などを経て、2011年より東京都医学総合研究所所長。医学博士。日本生化学会及び日本蛋白質科学会名誉会員、文化功労者。
世界のなかの生命科学という感覚
― 田中先生がHFSPグラントを受賞された当時のことや、HFSPの印象をお教えください。
遡れば早石 修先生がNIHグラントをもらいながら日本で研究していた逸話も有名で、当時、国際グラントの獲得にそこまでの気負いはなかったように思いますね。自然な流れで共同研究者から誘われ、申請の一部を分担し、HFSPグラントを受賞しました。英語での申請は実際問題エネルギーのいる仕事ですから、代表者ではなくチームの1員として狙うのも戦略です。もちろん、申請代表者としてHFSPグラントを受賞できるならさらに素晴らしいことですが。
それにしても、拠出率[1]に反して日本人によるHFSP受賞が少ないのはなぜでしょうか? 私の周りでも小松雅明君(現 新潟大学)くらいだと思います。正直に言って、HFSPを受賞できるレベルの研究者なら日本国内の研究費の獲得にも困らないでしょうから、採択率10%を下回る狭き門(HFSP)にわざわざ苦労してアプライしない、という判断もある。ただ、それ以上に「国際チームをつくる」ことに2つのハードルがありそうです。
1つはコネクションの問題です。いま留学する人が減っていますし、せっかく留学してもアカデミアから離れてしまう人も多いです。日本から一歩も出ずに世界と伍す研究者もいますが、それは特殊な例で、留学のような経験から得られる人脈なくして国際的な研究は成し難いです。論文や国際学会から知れる海外の研究事情はごく限られたものです。生命科学は日本だけのものではありませんから、海外の研究者との交流はそれ自体に大きな価値がある。若手の皆さんには、そのことに気づいてほしいと思います。
もう1つは日本のプレゼンスの問題です。3大陸にまたがる国際チームを推奨するHFSPでは、欧・米に続く第3極として日本が有力な候補でした。しかし最近ではその魅力が薄れてしまい、共同研究者として声が掛からない。モノ(設備)も、ヒト(人材育成)も、中国には「科研費倍増」くらいしないと張り合えないほどの差をつけられてしまったのですから。
[1] 現在、出資国のなかで最大の約40%(約2,000万ドル)を日本が負担
未完成=可能性
― 国際的にイノベーティブだと評価される研究課題はどのようなものなのでしょうか。
 私の受賞テーマであるプロテアソームも、小松君のオートファジーも、重要性が認められつつも未解決な、いわゆる「流行の」トピックだったのは事実です。しかし流行だから評価されるのかというと、それだけではないように思います。
私の受賞テーマであるプロテアソームも、小松君のオートファジーも、重要性が認められつつも未解決な、いわゆる「流行の」トピックだったのは事実です。しかし流行だから評価されるのかというと、それだけではないように思います。
印象的なことがありました。20年くらい前でしょうか、Salk研究所の友人を訪れた時にちょうどHFSPが話題になったのです。その友人がSalk研究所からHFSPグラントへ2件アプライしたことを知り、申請書を見せてもらったそうです。1件は業績欄がCNS誌で埋め尽くされているベテランチーム、1件はまだ論文もほとんどない若手チームからの申請でした。一見して若手の申請書の方がおもしろかったのですが、日本の基準で考えたら難しいだろうなという印象だったそうです。それが後日、受賞したのは業績のない若手の方だったと聞いて「あぁ、日本の研究費の審査とは違うな」と思ったことを覚えています。
HFSPは“できあがった”研究者には受賞が難しく、未完成であることに可能性が認められるわけです。この点を意識して、可能性ある日本の若手にはもっと積極的にアプライしてほしいですし、そのために申請をサポートするシステムも必要かもしれませんね[2]。
[2] 若手のHFSPへの応募につながるInterstellar Initiativeという事業が日本医療研究開発機構で始められている。
アイデアが先か,研究費が先か
― HFSPとは違うという、日本の研究費の現状について先生の実感をお聞かせください。
業績が偏重されているのが現実でしょう。研究費がとれず論文が出せない、論文が出せないから研究費がとれない、という負のスパイラルを回避するために、目先の流行にすがるしかないと思う人がいても無理はありません。しかし、例えばゲノム編集がすごいと追いかけても、追いついた頃には主要な課題の検討は終わっており、特許も押さえられている。流行を追えば一流誌に載る時代でもなくなりつつあります。
では、魅力ある研究計画はどのように立案すればいいのか? 良いアイデアがあるから研究費がほしい、というのが普通の考え方ですけれども、私は「真剣に研究申請書を書く」からこそ生まれるアイデアもある、と思っています。例えば「HFSPに応募できるくらいのテーマ」を考えることが、新しい展開を生むのです。
これはすべての研究費申請に言えることですが、大事なのは時間をかけて先へ先へと考えることです。ある研究領域が終わる1年以上前からチームをつくり、後続の領域の申請内容を練り上げ、完璧なプレゼンで研究費を獲得したような研究者もいます。その人は不採択だった時の展開まで考えていたそうですよ。真にオリジナルな研究をするには「余力」が必要なのです。
「余力」なき日本が生き残るには
― 「余力」がキーワードなのですね。もうすこし詳しくお教えいただけますか。
大隅良典先生(2016年ノーベル生理学・医学賞)がオートファジーの研究を始めたのは何歳の時だと思いますか? 40歳前後です。酵母のオートファジーの顕微鏡観察に成功してその遺伝子を発見したのは、43歳の時だったと聞いています。実績のない研究者でも「おもしろそうだから」という理由でポジションと研究費と時間が与えられる。研究者も「おもしろそう」という研究を楽しむ気持ちに忠実である。これが日本の「余力」でした。基礎生命科学研究において「ムダか? ムダでないか?」の判断はきわめて難しいものです。だからこその「ばら撒き」だったのです。
基礎科学研究予算が目減りしている現状の日本において、このような「余力」は失われつつあります。資源配分の効率化で事態をしのぐ他ないのですが、これも中々うまくいかないようですね。1つ例を挙げれば、この度の科研費改革では、若手の不公平感を緩和する名目で特別推進研究に生涯1回の受領制限が設けられました。結果はどうでしょう。特別推進研究に応募できなくなったシニアが基盤Sに流れ、本来であれば基盤Sを狙いたい若手が戦略的判断から基盤Aに申請せざるをえなかったと聞きます。大きな可能性の喪失です。要するに、科研費の総額を増やさない限り、手の打ちようがないというのが正直な感想ですね。
こうした問題に特効薬はないながら、私が希望を感じている日本ならではのシステムが2つあります。1つはJST(科学技術振興機構)の「さきがけ」で、ただ若手が登用されるというだけでなく、分野を超えた同期の間で人脈が形成されることが大きな価値になっています。もう1つは「新学術領域研究」の公募班で、こちらも若手が活躍する傾向があります。制度の拡充を期待したいところです。
科学に運はない,夢あるのみ
― 最後に、生命科学のフロンティアに挑戦するためのヒントをいただければ幸いです。
生命は本当に精巧にできています。未だ診断のつかない疾患に苦しむ患者さんもたくさんいらっしゃいます。研究すべきフロンティアが見つからない…なんてことはありえないのです。でも、「これを研究しなさい」という道は用意されていません。もしフロンティアが見つからないと思うなら、そのことに気づけていないだけなのです。最近はビッグラボ出身の業績ある研究者でも、自分の道を探すトレーニングが不十分なことが多い印象です。
現代進化論では木村資生先生の中立説が支持され、生き残るのは優れた個体ではなく、運のよい個体だと考えられています。では科学の世界で生き残るのはどんな研究者でしょうか? そこに運はありません。無から有は生まれませんし、有は無になりません。どんなに小さなことでも、それが修士論文の研究であっても、コツコツと自分の力で道を切り拓くことによって、それは個性となり、20年の時を経て花開きます。
経済成長を終えた日本では、もはや「生きるために裕福になろう」という価値観は通用しません。研究にも新しい価値観が求められています。それは利益を追い求める野心ではなく、私は科学に大切なのは「夢」だと考えています。考えてみてください。はるか宇宙を旅して小惑星の石塊を持ち帰った惑星探査機が、私たちの生活に目に見える恩恵をもたらす実感はありません。それでも小中高校生たちは、その姿を一目見るために列をなしました。憧れを抱いた子どもたちのなかから、未来を拓く人材が現れることもあるでしょう。生命科学も同じではないでしょうか。多くの人が基礎科学研究に本質的な魅力を感じています。その価値観を社会全体で共有するために、わかりやすい成功例を積み重ねていく必要があります。研究者一人ひとりが自分のモチベーションを全力でぶつけることのできる「夢のある科学」のため、これからも頑張っていきましょう。
――貴重なお話をありがとうございました。(聞き手:「実験医学」編集部)
最終更新日 平成30年4月3日