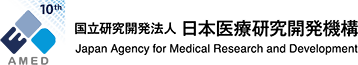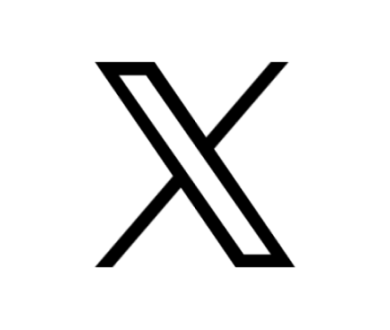HFSP受賞者インタビュー
HFSP 30周年記念スペシャルインタビュー ~これからの基礎研究と研究費を考える~
いま医学・生命科学研究の領域では、応用志向の強まりと基礎研究費の縮小に対する危機感が叫ばれています。一方で世界を見渡せば、HFSP(Human Frontier Science Program)という「純粋基礎研究のみ」を追求する大型の国際研究助成が、間もなく30年の歴史を数えようとしています。HFSPは15国・極の共同出資による事業で、1989年に日本の旗振りで始まったものです。大きく分けてグラント(3年で1億円を超える研究費)・フェローシップ(留学助成)・CDA(独立支援)の3つがあり、成果論文が国際平均の3倍の引用度を示すなど、その「目利き」が国際的に認められています。
今回、2019年にHFSP 30周年を控えるこの機会に、かつてHFSPグラントを受賞されたフロントランナーの先生方に、基礎研究の“フロンティア”に挑戦すること、そのための研究費を獲得する戦略について、あらためてお語りいただきました。研究者の自己実現に役立つヒントが満載ですので、ぜひご一読ください。

- <インタビュー>
- 本庶 佑 先生(京都大学高等研究院)
- <グラント受賞テーマ>
- DNA再構成とリンパ球分化の制御(1990年)
- <プロフィール>
- 1942年生。米国留学後、大阪大学医学部教授、京都大学医学部教授、同医学部長、文科省高等教育局科学官、JSPS学術システム研究センター所長、総合科学技術会議議員を歴任。専攻は分子生物学。日本学士院会員、2013年文化勲章、2014年唐奨受賞。現職は、京都大学高等研究院特別教授、先端医療振興財団理事長。
協調と競争のHFSP
― 先生は創設間もない1990年にHFSPグラントを受賞されています。当時を振り返ると、先生にとってHFSPはどのようなものでしたか。
1987年のヴェネチア・ サミット前に、中曽根康弘首相(当時)と面会する機会がありました。当時の日本は、1970年代後半から国際的に続いていた「組み換えDNA論争」に反対の立場を明示しようと検討していたようです。それにより生命科学の主導権を握りたかったのですね。しかし私は「どうせなら前向きな提案をしませんか」と中曽根首相に進言しました。それがどう響いたかはわかりませんが、結果として日本は同サミットでHFSPの創設を提唱しました。その後HFSPが世界に認められ、生命科学の発展に貢献してきたのは喜ばしいことだと思います。
私がHFSPにアプライした当時、「DNA再構成とリンパ球分化の制御」というテーマは国際的に競争の激しい分野でした。だからこそ多国籍チームの編成がうまくいったとも言えます。「協調」と「競争」には同一な面があるのです。HFSPはまさにそれを体現しているように思います。
でも、日本からの応募は少ないのですよね。残念なことです。フェローシップ(留学助成)の審査員を務めたこともありますが、やはり他国に比べて少なかった。私の研究室からHFSPフェローシップを受賞したのも2人くらいしかいません。その1人がPD-1を発見した石田靖雅君です。
申請書を英語で書くハードルもあります。しかしそれ以上に教育の問題がある。日本は「言われたことを上手にこなす」ことが評価されがちです。時にはボスとも反発しあうほど「自分勝手」できる人でないと、独創性あるテーマを立ち上げ、他の研究者を説得することは難しい。HFSPに応募するくらいの研究者が増えれば、日本の生命科学もより本物になったと言えるでしょうね。
解らないことだらけの生命科学
―「協調」に関連して、HFSPではイノベーティブな研究には学際融合と国際連携が不可欠とされていますが、先生のお考えになるイノベーティブな研究の原動力はなんでしょうか?
HFSPが異分野間の共同研究やテクノロジーの融合を奨励するのは、1つのスタイルとして納得のいくものです。喩えるなら「接木」でしょう。質のよい果樹どうしを接いでより美味しい果実を得る。ただ、これだけではそもそも木のないところには何年経っても実がならない。
生命科学の基礎研究には「種蒔き」が必要です。これはHFSPではなく科研費の役目です。「ばら撒き」と批判されることがありますが、残念ながらそれは生命科学のことをよく知らない方の発想ですね。応用に近い工学のような分野はrequirementがはっきりしているので、そこに向けてしっかりデザインされた研究に集中投資されてしかるべきです。でも、生命科学は違います。「何から手を付けるか」から考えねばならないほど解らないことだらけ。出口に向かって研究をデザインしようなんて考えたら、ほとんど失敗しますよ。
生命科学の基礎研究は、蒔いた種の10%から芽が出れば上出来です。苗になるのはそのうちの数%。さらに木にまで育つのはその数%。最後に実がなるとなればもっと確率は減る。その実が美味しい確率なんて、万に一つです。しかし種を蒔かなければ芽は生えません。米国から苗を買って植えればいいような時代は明治で終わったのです。
「PD-1」の基礎研究もまさに「ばら撒き」の成果です。何もないところからPD-1分子を同定したのが1992年。それが免疫反応の負の制御因子であることを突き止めるだけで6年の月日がかかった。誰が今日のがん免疫療法への展開を予想していたでしょうか。
科学研究費“補助金”は真なる科学研究費になってほしい
― 蒔きたい種はあっても蒔くお金がない、という声が基礎研究者の間で強くなっています。いまの研究費事情を先生はどのようにご覧になっていますか?
 「ばら撒き」を担っていた運営費交付金が削減の一途をたどるいま、大学は独立基金を設立して研究者の自由を守るような努力が必要です。それがない現状では、科研費の基盤研究が文字どおり「基盤」の役目を果たしています。しかし科研費はいまだ「科学研究費“補助金”」を自称し、内実も補助金の域を脱しないことが問題です。最低でも1件2~3千万円はないと研究費として十分とはいい難いでしょう。大型研究費の額を削ってでも裾野を広げてほしい。1人で何億円もの研究費をもらっても正直その価値は薄まると思います。私の経験で言えば20人のチームが限界でした。50人ほどになった時期もありましたが、誰が何をやっているのか把握できなかった。不幸なことに研究にかかるお金が膨らんでいるのも事実ですが、研究費さえあれば優れた研究をできるわけでもないのです。
「ばら撒き」を担っていた運営費交付金が削減の一途をたどるいま、大学は独立基金を設立して研究者の自由を守るような努力が必要です。それがない現状では、科研費の基盤研究が文字どおり「基盤」の役目を果たしています。しかし科研費はいまだ「科学研究費“補助金”」を自称し、内実も補助金の域を脱しないことが問題です。最低でも1件2~3千万円はないと研究費として十分とはいい難いでしょう。大型研究費の額を削ってでも裾野を広げてほしい。1人で何億円もの研究費をもらっても正直その価値は薄まると思います。私の経験で言えば20人のチームが限界でした。50人ほどになった時期もありましたが、誰が何をやっているのか把握できなかった。不幸なことに研究にかかるお金が膨らんでいるのも事実ですが、研究費さえあれば優れた研究をできるわけでもないのです。
ただ、研究費の偏りを避けることは大切ですが、2018年度の特別推進研究[1]の変更は「改悪」だったと思います。1人の研究者が生涯を通じて1度限りしか受領できなくなりました。種から出た芽は木になり、いつか朽ちることもあるでしょう。その時はやめればいい。しかし、はじめから年限で区切るというのはどういう意図なのでしょうか。PD-1の例でおわかりのように3年や5年で「格段に優れた」成果が出ることは稀ですし、1人の研究者は1つのテーマしか大成しないなんて決まりもない。HFSPだって異なるテーマで複数回受賞する研究者もいるわけです。研究費の運営に携わる方には、生命科学の基礎研究を理解した、より柔軟な考え方を期待しています。
[1]「新しい学術を切り拓く真に優れた独自性のある研究」を支援する科研費。HFSP同様、最高峰とされる。
成功とリスクは背中合わせ
― 基盤的研究費の状況が厳しいなかで、若手研究者が自分が本当にやりたい研究を貫いていくためにはどうすればよいのでしょうか?
まず自分は研究者になって何をしたかったのか、自問してみてください。研究者になった時点で世間的な安定とは縁遠い「変わり者」です。平凡な人生を求めるなら他の道がある。失敗してもなんとかなりますし、むしろ失敗しない人生なんてつまらない。大切なのは失敗した時にどうするか、です。失敗から生まれる発見がある。安全志向からは得られないものがあるんです。研究者は金銭的に不安定と言われますが、私が助手の頃の給料なんて今の1/10くらい貧乏でしたよ。成し遂げたいことがあるならば、必要なリスクは積極的にとるべきなのです。
私の最大のリスクテイクは留学でした。当時は国内にポジションを得たうえでの期間限定の留学が普通だったのですが、私は何の保証もなしに京都大学を飛び出しました。帰国後、いっさい後ろ盾のない東京大学に職を得たことも私に幸運をもたらしました。自由と引き換えに成果を求められました。追い込まれた環境が、力になったのです。成功とリスクは常に背中合わせなのです。
最近は留学をしない人も多くなりましたね。インターネットで世界中の情報が手に入る時代ですが、画面越しに見るのと、肌で感じるのとは違います。異文化とのふれあいは人生観を変え、自国の文化を見直す機会を与えてくれます。吸収力の高い若いうちに留学しないのは、何物にも代えがたいマイナスです。HFSPフェローシップのような留学助成は活用するべきですし、留学してこそ得られる濃い友人関係が、HFSPグラントのような国際共同研究にもつながっていくのです。
目の前に広がるフロンティアに挑もう
― 最後に、いま生命科学のフロンティアはどこにあるのか、先生のお考えをお教えください。
私のキャリアのはじめは分子生物学の勃興期でしたから、「分子を見つける」ことが最大の関心事でした。その時期がすぎると、それぞれが見つけた分子を深掘りする段階になりました。その流れの果てに、生命科学は全体を見ずにnarrow slitから一面だけを覗くような学問になってしまいました。
生命はシステムなんです。全体像を見なくてはならない。神経系、免疫系、代謝系…と細分化されたものではなく、本当の意味での生命そのものです。そのためのテクノロジー、すなわちメタボローム解析やエクソーム解析が今そこにあるのですから、活用する方向に向かわないといけません。難しいことですが、進化がその手がかりになるかもしれない。Theodosius Dobzhanskyが40年前から"Nothing in biology makes sense except in the light of evolution."と述べているように、進化の視点の欠けた生命科学などありえないのです。
――貴重なお話をありがとうございました。(聞き手:「実験医学」編集部)
最終更新日 平成30年4月3日