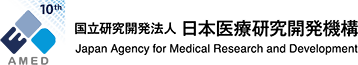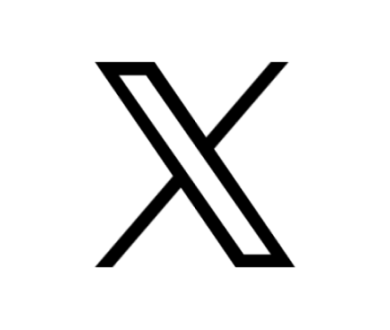HFSP 30周年記念スペシャルインタビュー
HFSP 30周年記念インタビュー ~これからの基礎研究と研究費を考える~
いま医学・生命科学研究の領域では、応用志向の強まりと基礎研究費の縮小に対する危機感が叫ばれています。一方で世界を見渡せば、HFSP(Human Frontier Science Program)という「純粋基礎研究のみ」を追求する大型の国際研究助成が、間もなく30年の歴史を数えようとしています。HFSPは15国・極の共同出資による事業で、1989年に日本の旗振りで始まったものです。大きく分けてグラント(3年で1億円を超える研究費)・フェローシップ(留学助成)・CDA(独立支援)の3つがあり、成果論文が国際平均の3倍の引用度を示すなど、その「目利き」が国際的に認められています。
今回、2019年にHFSP 30周年を控えるこの機会に、かつてHFSPグラントを受賞されたフロントランナーの先生方に、基礎研究の“フロンティア”に挑戦すること、そのための研究費を獲得する戦略について、あらためてお語りいただきました。研究者の自己実現に役立つヒントが満載ですので、ぜひご一読ください。

- <インタビュー>
- 永田和宏 先生(京都産業大学)
- <HFSPグラント受賞テーマ>
- Cell Stress and Proteostasis Dysfunction in Aging and Disease(2011年)
- <プロフィール>
- 1947年、滋賀県生。京都大学名誉教授。京都産業大学タンパク質動態研究所所長。元日本細胞生物学会会長。専門は、小胞体におけるタンパク質の品質管理機構の研究。1986年、コラーゲン特異的分子シャペロンHsp47の発見以降、品質管理に関わる新規因子EDEM、ERdj5などを次々に発見。2009年、紫綬褒章受章。2017年、ハンスノイラート賞受賞。著書に『タンパク質の一生』(岩波新書)『生命の内と外』(新潮選書)など多数。
サイエンスは文化である
― 昨今、基礎研究、特に出口が見えにくい萌芽的な研究をどう支援するかについて議論がなされています。永田先生のお考えをお聞かせください。
私も基礎研究をずっとやってきた人間なので、今すぐ役に立つのか、ということはよく聞かれて来ました。私はもともと湯川秀樹さんの講義を聞きたくて京都大学の物理学科に入りました。湯川さんが講義で言ったことで強く覚えているのは、「いま役に立つ、ということは10年後20年後30年後にはほとんど役に立たない。いま役に立つ、ということは環境が変わったら役に立たない」ということです。ですから、現在役に立つかどうか、という尺度だけで見るのはある意味危険で、まずはスペクトラムを広げておくことが非常に大事だと考えています。
私は大隅良典さんが設立された大隅基礎科学創成財団の理事もやっていますけれども、その財団の基本的な尺度もそこにあります。大隅さんが言っているのが「サイエンスは文化だ」ということです。私たちは文化振興を議論する時に、それが役に立つかどうかでは評価しないわけですね。例えば、陸上の100 m走で桐生祥秀選手が日本人として初めて10秒を切りました。それは誰の役に立つものではありませんが、でもやはり私たちはそれを期待していました。他の例では、生命科学の分野でいうと、私たちの体の細胞の数は60兆個と言われていたのが、2013年に37兆個という話になりました。60兆が37兆になっても誰も得をしませんが、やはりそこには真実があって、私たちもそれを知りたいという気持ちがどこかにあるのです。それはすごく大事な点だと思います。サイエンスは文化の一つ、と捉えないとその重要性は見えてきません。そのためには、一般の人に「基礎研究は大事だ」と言うだけではなくて、サイエンスでわかった知識が一般の人にとっても知ることの喜びにつながっていかないと駄目なのです。これまで、私たちが感じてきたサイエンスに対する喜びを一般の人に還元してこなかったことも、いまの状況を形作ることに繋がっていると思います。
― いまのグラントのシステムから見るといかがでしょうか?
グランティングというのは国にとって言わば投資対象なのですが、この投資が5年とか10年という短いスパンで切られてしまうのは問題だと感じています。その期間をもっと長く見ることが必要だと思います。よく言われるように、ノーベル賞を取るのは30年前の仕事なのです。それから、基礎研究を支援して欲しいと言っても、すべての研究費がバラマキでいいと考えているわけではありません。やはりある種の集中というのは必要です。ですが、いまのように運営費交付金が削られている状況においては、芽が育つことが難しくなってしまっています。今のうちに何とかしておかないと、日本のサイエンスは将来絶対駄目になってしまうと感じています。
1つのラボでできないことにチャレンジする
― 永田先生は2011年にHFSPグラントを受賞されていますが、どのような形で始まったのですか?
興味はある程度似ているけれども、違う実験系を持っている者同士で集まって、何か一つのラボ ではできないことをやりましょう、というのが私たちの基本理念です。ぶっちゃけて言うと昔からの仲間が集まったということですが、私たちは哺乳類のシステムを持っていて、ノースウエスタン大学のRichard Morimotoは線虫のシステムを持っています。特にエイジングのような時間軸を対象とする研究は、哺乳類のシステムではなかなか扱うことができなくて、一方線虫はバイオケミストリーがほとんどできません。そこで、お互い補い合うような形でプロジェクトが組めたのはすごく大きいですね。
とにかく非常にチャレンジングな研究を気楽にさせてもらっています。山中伸弥さんが言うように、プロ野球だったら3割打てば大打者、サイエンスでは1割打っていたら大成功、というところがあります。私たちは幸いこの共同研究から、それぞれのメンバーをco-authorsとして論文をまとめることができました。しかし、たとえ論文としての結果は出なくても、それが知識や方法論として蓄積されることが、非常に大事なHFSPの目的の一つでもあると思います。それから、協力体制を構築したり、新しいシステムを導入したりすることにも価値があります。私たちのところで言うと、ぞれぞれの研究室の若手のジュニアファカルティーに責任を持たせていたのですが、彼らが主にSkypeを使って毎週のように議論をしながら申請書のドラフトを書いていったのです。彼らにとって非常に大きな財産になったと思うし、そういうことはなかなか科研費ではできません。大きな自信になったと思いますね。HFSPグラントは金額だけで言うとそれほど大きなお金ではありませんが[1]、若手が海外の若手と共同でアイデアを出し合って方向性を考えていく、そして成果をうまくまとめていった、その間になされたディスカッションのプロセスこそが非常に価値があると思います。
[1]3年間で最大135万ドル。
年に一度は海外からinviteされる研究者になれ
― 若手の研究者の場合、海外の異分野の人とコラボレートしながら計画を練っていくのは敷居が高そうに感じます。
そうですね。まずは国際的なネットワークを持っているということが大事です。そのためには、いろんなチャンスに海外に出て、そこで面白い仕事をしている人と実際に顔を合わせて、たくさんのディスカッションをすることが必要です。実際に行って話をしてまだ論文になってないアイデアをそれぞれ交換するというプロセスでしか、共同研究は成り立たないのです。サイエンティストも人間だから信頼感こそが大事です。せっかくHFSPのようなグラントがあるのだからそれに応募するためでもいいし、応募した後でもいいけれど、国際的なネットワークの下で仕事をするという経験を若い方々が積んでおくことが大事だと思います。
そのためには、いまの若い人はもっと海外の学会に行った方がいいと思います。年に2、3回は自費でも海外に行くぐらいでなければいけません。日本国内でコミュニティができてくると、その中ですごく互いにリコグナイズし合ってしまって、自己満足に陥ってしまいます。海外も含めたコミュニティの構築を意識して欲しいと思います。

仕事をする場は世界
― 最後に基礎研究を追求する若い研究者へのメッセージをいただけますか.
日本は若手がお金を取って早く独立することに対してもっとアグレッシブであって良いと思います。米国だと、ポスドクで雇われるとすぐにPIになろうとするのに、日本ではボスに任せておけばそのうちどこかを紹介してくれるだろうと期待しているところがあります。以前は、日本ではポスドクがお金を取れないシステムだったこともあるかもしれませんが、若いうちからどうしたらお金が取れるか、ということをもっと自分で考えないといけません。そうすれば、ラボ経営の難しさも自分で分かるし、お金を取る難しさもそれで成果を出していくしんどさも分かります。それでやっとサイエンスをやる基礎ができるわけです。そのためにはシニアな研究者がもっと若手をエンカレッジすべきだと思います。
それから「仕事をする場は世界である」ということをきちんと認識することが大事です。論文を書いて国際的なジャーナルに発表するだけでは不十分です。世界に実際に出て行って、英語でディスカッションをし、無駄話もできるような関係を作っていく。サイエンスの最大の喜びは、結局はディスカッションだと思うんです。「こんなデータが出たけどどうや」みたいに、レスポンスを直接聞ける喜びがあったから、私もこれだけ長いことサイエンスの場にいたんだと思います。
私のラボからNIHに行って、あっという間にPIになった女性がいます。彼女を見ていると日本にいる必要は全然ない、ということを感じます。サイエンティストの仕事をする場は世界です。日本人の若手の皆さんが、単に職業としてではなくて、サイエンティストとしての喜びを感じながら世界で仕事ができるような研究者になってほしいと思います。
――貴重なお話をありがとうございました。(聞き手:「実験医学」編集部)
最終更新日 平成30年4月3日