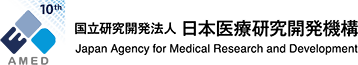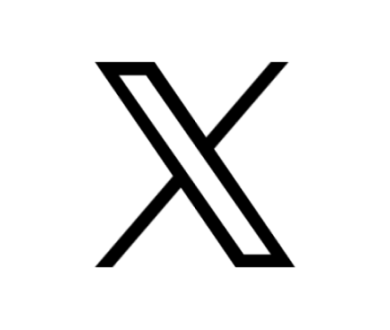HFSP受賞者インタビュー「いま考える、国際連携・異分野連携のチカラ」
いま日本の医学・生命科学研究は国際競争力の低下が指摘されています。様々な要因が考えられるなか、「研究人材」の観点からは国際頭脳連携の推進、「研究資金」の観点からは国際化と新興・融合領域への挑戦促進が政策レベルのキーワードとして挙げられています。一方、国際化や異分野融合がことさら強調されることに対し、現場からは「本質的でない」との意見も出ています。視野を広げてみますと、創設以来InterdisciplinaryとInternational(Intercontinental)を採択基準としてきた国際研究助成プログラムHFSP(Human Frontier Science Program)が、制度として世界的に高い評価を得ているという参考事例もあります。そこで今回、HFSP研究グラントの受賞経験があり、研究者として存在感ある活動をされている先生方に、国際連携や異分野連携の意義についてお考えを伺います。キャリア戦略のヒントが満載ですので、ぜひご一読ください。
※雑誌『実験医学』とのコラボレーションによるスペシャルインタビュー企画です。
国際連携・異分野連携は「自分のやりたいこと」を追求するためのプロセス

- <インタビュー>
- 森 郁恵 先生(名古屋大学大学院理学研究科 ニューロサイエンス研究センターセンター長)
- <プロフィール>
- 1980年お茶の水女子大学卒業、1988年Washington University大学院修了(PhD)、1989年九州大学助手、1998年名古屋大学独立助教授、2004年同大教授、2017年同大理学研究科附属ニューロサイエンス研究センターセンター長。受賞歴:2006年猿橋賞、2016年中日文化賞、2017年紫綬褒章など。
- <HFSP研究グラント受賞テーマ>
- 1992年:Learning and memory in the nematode, C. Elegans: behavioral, cellular and molecular analysis
1997年:Perception of odors, tastes and temperature: attraction and aversion of C.elegans
2001年:Functional analysis of sensory circuits in C. elegans
※ 取材:2019年12月(情報は取材当時のものです)
国際連携は研究者の「自然」
―― 先生はHFSP研究グラントを3度受賞されるなど、国際連携の意識が強いようにお見受けします。先生にとって国際連携の意義とは何でしょうか?
科学研究者である限り、国際連携は「自然」なことだと思っています。研究は日本だけのものではありませんから、自分の主張を認めてもらうためには世界とevenでなければ。論文発表にしても、査読者は世界中の研究者です。お互いを知っているかどうかは結果に影響して当然です。査読で止められ、裏で出し抜かれることもあるかもしれません。ただ、それも研究者としての価値を認められてこそ。認められれば「温度走性のことならイクエに聞いてみよう、共同研究しよう」のように連携が生まれます。科学研究では国際的な連携と競争が自然に起こるはずです。
「出会い」が研究者としての自己をつくる
―― 先生は学位留学をされていますね。国際連携の重要性を理解してのことだったのでしょうか? 海外での経験はその後のキャリアにどのような影響がありましたか?

私の出身大学には博士課程がなく、「博士号をとるなら留学で」という空気だったのが実際のところです。「生物の行動の遺伝的背景を理解したい」という一貫した興味のなかで、修士までの集団遺伝学のアプローチに限界を感じたこともあり、あるラボに内定をもらい留学しました。米国の大学院にはローテーション制度があるため、内定の有無に関わらずいくつかのラボを回ってから所属先が決まるのですが、ここで問題が起こりました。私はローテーションの途中で、内定ラボとは別のラボで線虫(C. elegans)に興味をもち、居着いてしまったのです。Sydney Brennerの最初の弟子の1人[1]、Robert Waterston(以降、Bob)のラボでした。
Bobは研究に厳しく、データが出るまで何カ月も話す機会すら与えられない、ということもありました。でも影で、ローテーションの決まりを破り、内定も蹴ったことで非難される立場にあった私を守ってくださっていたようです。後になって近しい人から「Bobは、イクエは私のラボに一番フィットする“リガンド”だから、と言っていたよ」と聞きました。Bobのおかげで私は、自分の興味を追求する道を進めたわけです。
その後、家族の事情などで日本への帰国を決心しました。Waterstonラボの仲間からは「日本は男尊女卑と聞いている。嫌になったらいつでもアメリカに帰っておいで」とラボの鍵を渡されて。さらに、当時の日本では主要大学に線虫研究者がおらず、コネのない私は学会でポスター発表の機会を得るだけでも一苦労でした。
なんとか日本でポジションを得て温度走性に取り組み、成果が出始めて線虫の国際会議[2]で口頭発表の機会を与えられた時のこと。「時間もないし、どうせわかってもらえないだろうけど」と思いながら、AIYという介在神経に関する仮説を一瞬だけスライドで写しました。すると、内容を的確に把握し、後で声を掛けてくれた人がいたのです。Cornelia Bargmann(以降、Cori)でした。彼女の頭の中には私と同じ神経回路マップが描かれていて、ディスカッションが弾みました。その時から、Coriは私の唯一無二の理解者、そしてライバルです。私がHFSP研究グラントを受賞できたのも、Coriがチームメンバー[3]として私に声を掛けてくれたからです。Coriに出会わなければ、今の私はなかったでしょうね。
[1] 線虫がモデル生物としての地位を確立するまで、「Sydney Brennerのラボに行くなんてキャリアをドブに捨てるようなものだ」という評価だったという。Waterson博士をはじめ、当時のBrennerラボに集まった面々がいかに“目利き”だったかが窺える。
[2] International C. elegans Meeting(現International C。 elegans Conference)。
[3] 申請要件として、通常3人程度の、異なる大陸にいて、異なる専門性をもつ研究者でチームを組む必要がある。
強制はナンセンス…でも
―― グローバルな出会いが自己実現につながるのですね。では先生は、国際共同研究でなければ申請できないグラントや、海外経験がなければ応募できないポジションには賛成でしょうか?
大切とはいえ国際連携は科学研究の「プロセス」にすぎませんから、プロセスの目的化は問題です。ただ、今の教育現場ではマイクロ・マネジメント[4]が必要な場合も少なくない。難しいことですが国際連携も、強制しつつ「自分からそうした」と思わせるような折り合いをつけていくべきなのかもしれませんね。
ここまで話してきたように、人との繋がりは研究の力になります。有名ラボに留学して箔をつけようとか、最新の技術を身につけて帰ってこようとかではなく、3~4年かけて世界の研究者とその価値観にしっかり触れるべきです。異文化への理解は、多様性を増す日本で教育・研究に携わるうえでも力になります。「廊下でノーベル賞級の研究者と日常的にすれ違う」ような環境に身を置くのもよいですよ。ノーベル賞をとる研究がどんなものか肌でわかりますし、ノーベル賞は意外と身近にあるという感覚が、若手人材のモチベーションにつながるからです。
「国際化なんて手間が増えるばかりだ」と否定的な意見もありますが、「お膳立てされている機会を活かそう」という発想の方がよいのではないでしょうか。
[4] 目標とそれを実現可能なプロセスの設定、時間管理にいたるまで、詳細な報連相を求めながら進めるタイプのマネジメント。
心の「受容体」を発現させよう
―― もう1つのキーワード、異分野連携についてはどのようにお考えでしょうか。
線虫の国際会議では、元々、1つの会場で発生、老化、細胞死、脳神経…と分野の垣根なく議論していました。私にとっては異分野連携も国際連携と同じくらい自然なものです。それが日本では、異分野連携というと「総花的」になり、連携がうまくいかないと言われます。私は「Interstellar Initiative」[5]のプログラムオフィサーをしているのですが、ここでも異分野の研究者どうしが物別れに終わることがあります。なぜでしょうか。
そもそも連携が求められるのは、研究者が「分野」で縦割りになり横のつながりが弱いからで、これは「組織」が原因です。多くの研究者は、研究機関の特定の部門、特定の学会に所属しますよね。それで学会に参加しても、例えば「幹細胞研究者」ならタイトルに「幹細胞」とあるセッションを見て帰る。組織に研究が縛られているわけです。自分はこうでなければ、という思い込みが壁になる。だから連携が難しいのです。
そんな時、私はよく「心の受容体を発現させなさい」と言います。「受容体」は教養と言い換えてもよいかもしれません。幹細胞に興味があるなら、例えば「昆虫」という「リガンド」が与えられた時、成虫原基のシステムに何かヒントがあるかも? のように反応する「受容体」をもっているか。この「受容体」が異分野連携の鍵であり、研究に新しいアイデアをもたらすものなのです。論文を読むにも、キーワードで検索して引っかかったものだけ、ではダメ。Natureを冊子で読むのが普通だった時代には、パラパラめくって思いもよらない「受容体」を発現させたり、「リガンド」を受け取ったりできました。若い方は意識してそのような機会をつくることが、研究力につながると思います。
[5] 日本をはじめ異なる国・異なる分野の若手研究者を3人1組に編成し、医学・生命科学分野の難課題に対する研究計画の立案を求めるワークショップ(AMED事業)。
トレンドは乗るものではない、つくるもの
―― 最後に、国際連携や異分野連携を模索する読者に向けて、メッセージをお願いします。
「留学して分野を変えようと思うんです」という相談を受けることがあります。国際連携、異分野連携の時代に合っていますよね。興味の追究に突き動かされた自然な留学は応援します。でも多くの場合、私の答えは「No」です。ただトレンドに乗っかりたいだけ、という気持ちが透けて見えるからです。研究者にとって、トレンドはつくるもの。トップジャーナルを読み込んで立てた完璧に見える研究計画が、下手をすれば剽窃になっている、ということもあります。私の留学先のジャーナルクラブでは、いわゆる三大誌の紹介はご法度でした。求められたのは、次に三大誌に載るような種を見つける「目利き」であれ、ということでした
国際連携、異分野連携で大切なのは、それが「自分のやりたいこと」を成し遂げるためのプロセスだと考えること。そして、それを実現可能なパートナーを見出す「目利き」であることです。その点でHFSPの研究グラントは、チームビルディングの段階で値踏みし値踏みされ、審査の段階でその目利きを評価され、と最高のトレーニングになります。英語での申請がネックと感じる方がいるかもしれませんが、チームなので、英語の得意なネイティブに代表として申請書を書いてもらうのも戦略上有効です。まずはチャレンジしてみてください。
―― 貴重なお話をありがとうございました。(聞き手:「実験医学」編集部)
最終更新日 令和2年3月25日